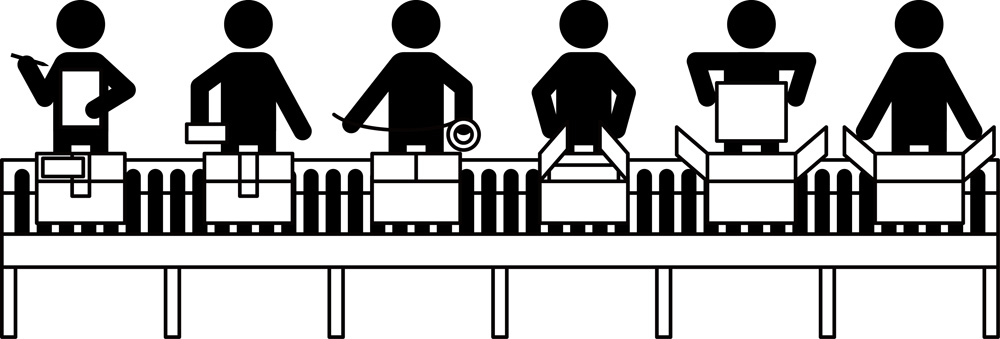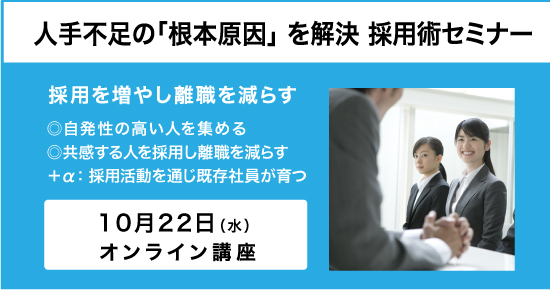250年前の名著から紐解く、働き方のアップデート法
指示ゼロ経営では「ひとしごと」という働き方を推奨しています。
製造現場で言えば、ベルトコンベアに乗って工程の一部分を行うのではなく、「セル方式」のように1人、もしくは小集団で完成品を作るというやり方です。
あるいは、一部分を担当したとしても、工程の計画づくりや、業務の改善活動…「上流」の部分に参画することです。
要するに、上の者が決めた計画の一部分をやらされるという状態をなくしたいのです。
なぜ、僕が「ひとしごと」を推奨するのか…今日の記事で改めて確認したいと思います。
分業の概念を初めて提唱したのはアダム・スミスだと言われています。
1776年に出版した「国富論」の中で、分業化がいかに生産効率を高めるかを説明していますが、一方で負の側面も指摘してます。
それは、
「分業によって、自分の能力以下の仕事を果てしなくやらされることになった労働者は愚か、無知になり、精神が麻痺してしまう。彼らは理性的な能力も感情的な能力も失い、ついには肉体的な活力さえも腐らせてしまう」
と、恐ろしい指摘をしています。
当時は、モノを手に入れること=幸福だったので、大量生産を実現する分業化は無条件に受け入れられました。
労働者も、退屈な仕事であっても、それが豊かな生活に直結することが分かっていたので我慢することができました。
しかし、今、負の側面が顕在化しています。
モノが過剰な時代になると、モノの充足=幸福という公式が成り立たなくなり、人々は生きる意味が分からなくなりモチベーションの維持が難しくなります。
リーダーは意味を創り、働き方をアップデートする必要があると思うのです。
意味づくりに関しては、有名な「3人のレンガ積み職人」の逸話が参考になります。
旅人が3人のレンガ積み職人に出会う話です。旅人が何をしているのか?と尋ねると1人の職人は「見れば分かるだろ。レンガ積みをしているのさ。毎日大変だよ」と答えた。2人目の職人は「大きな壁を作っているんだ。これが自分の仕事だ」と答えた。3人目の職人は「オレたちは歴史に残る偉大な大聖堂を作っているんだ」と答えたという話です。
指示ゼロ経営では、例え、レンガ積みという分業化された一部分を担当していたとしても、大聖堂を作るという目的のために行っているのではれば「ひとしごと」と捉えます。
分業による、もう1つの負の側面は部分最適の弊害です。
ナチス・ドイツのホロコーストは、分業化によって起きたと分析されています。
名簿づくりや移送の担当者は、全体の一部分だけを担っていたので、罪の意識がなかったと言います。このように、責任意識が欠如した個人の連結によって、あの恐ろしい虐殺が可能になったということです。
もし、これが1人がすべてを担当、実行、あるいは「大量虐殺」という目的を共有した上での分業…つまり「ひとしごと」であれば、組織的な仕事はできなかったかもしれません。
企業が悪事を働くことは稀ですが、一部分しか見えていないことで、全体成果への貢献ができなくなることは頻繁に起こりますので注意が必要です。
アダム・スミスの国富論からおよそ250年が立ち、時代が一周した感がありますが、そんな今だからこそ、働き方のアップデートを真剣に考える時に来ていると思います。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
※年内最後の採用術セミナーを10/22(水)に開催
✓自発性の高い人材がたくさん集まる
✓面接時の情熱とヤル気が入社後も続く
✓先輩社員が新人の教育に関心を持ち共に育つ