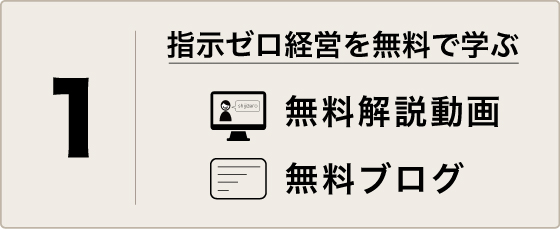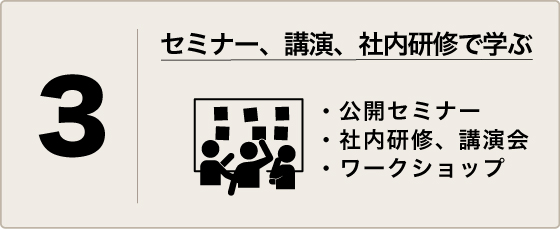滅私奉公から「活私奉公」へ…個人と組織の新しい関係
日本には昔から、私心を捨て公に尽くす「滅私奉公」の美徳がありますが、今は、自分を活かし全体に貢献する「活私奉公」が時代の感性に合っていると思っています。
大量生産の時代では、人材は均質化された歯車であることが求められましたが、今は独自性や斬新性が求められます。
そのためには、個性を存分に発揮し組織に貢献する活私奉公型の人材が必要です。
変革はいつも少数派から始まります。少数派が考える「変なこと」を多数派が受け入れた時に全体が変わります。なので、働き方を変えるためには、少数派を大切にする必要があります。
ところが、日本には、村社会型の組織が多く、この壁は大きい。
日本の村社会の歴史は、武家社会にまで遡ると言われています。武家社会では、「集団の秩序維持を最優先する」「君主の為なら不正を厭わない」という滅私奉公を美徳としました。
この価値観を維持するために、滅私奉公をよしとする教育が行われてきました。その顕著な表れが、道徳の教材「星野君の二塁打」だと思います。
.
❚ 「星野君の二塁打」という教材
「星野君の二塁打」は要約するとこんな話です。
・星野君は少年野球チームの選手。ある公式戦でのチャンスに星野君に打順が回ってくる。
・ここで監督が出したのは、バントのサインであった。
・しかし、星野君は打てそうな予感がしてバットを振り、結果二塁打を放つ。
・この二塁打でチームは勝利し、チームは選手権大会出場を決めた。
・しかし翌日、監督は「チームの作戦として決めたことは絶対に守る」という監督と選手間の約束を持ち出し、みんなの前で星野君の行動を咎める。
・「いくら結果がよかったからといって、約束を破ったことには変わりはない。犠牲の精神の分からない人間は、社会へ出たって、社会をよくすることなんか、とてもできないんだ」などと語り、次の試合に先発出場させないことを宣告する。
この教材は、集団と個人の関係を考えるために長く使われてきましたが、時代の変化を受けて2024年に廃止されました。
.
❚ 「俺を見るな。自分で考えろ」
フィリップ・トルシエ氏がサッカー日本代表の監督に決まり来日した際に、日本には、車が一台も通っていないのに赤信号で待つ人が多いことに驚いたという話があります。
この話が紹介されると「法律なんだから当然だ」という反論が多く上がりました。
ルールだから無条件に守るという日本人と、市民の力で体制を転覆させた経験があるフランス人との違いということでしょうか。
確かに、日本人は非常に秩序正しいわけですが、一方で「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という性質もありますね。
これは、良くも悪くも日本人の村社会を象徴していると思います。
トルシエ監督は、選手に対し「ピンチの時に監督を見るヤツはダメ」と教え、自ら考えることを求めました。
.
❚ リーダーシップの本質は「敷居を越える」
リーダーシップの語源は「Lead」ですが、これは元々「敷居を越える」という意味の「Leith」という古代語から派生しているそうです。
これに習えばリーダーの役割は、敷居を越えるために少数派を支援すること…「活私奉公」の推進を行うことではないでしょうか。
その事例として、緊急時に自分で判断し行動をしたバス運転手の逸を紹介します。
1990年、名古屋市営バスの運転手だったKさんは、乗客を乗せての任務中、道路に倒れている女性を発見します。
女性は頭から血を流して意識はありませんでした。Kさんは、二次被害を防ぐため、交通量の多い車線の真ん中にバスを停め、後続の車を止めました。
しかし、消防署が近くにありながら、10分経っても救急車が到着しません。Kさんは、「救急車は出払っている」と推測し、「一刻を争う事態」と判断。バスで女性を病院まで運ぶ決断をします。
病院に行くためには路線を外れる必要があります。同社には「路線を外れてはいけない」というルールがあります。
それでも、Kさんは女性を病院に運び、おかげで女性は一命を取り止めます。
バス会社はKさんの判断をどう裁いたでしょうか。
結果は、ルール違反を罰することなく、そればかりか社会に感動を与えた人を顕彰する「シチズン・オブ・ザ・イヤー」を授与しました。
滅私奉公は、集団で画一的な行動をする時には有効ですが、多様化が求められるフェーズには向いていません。
星野君やKさんのように、状況を見極め、勇気を持って行動する力が求められると思います。
あなたは、どんな敷居を超えますか?
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。