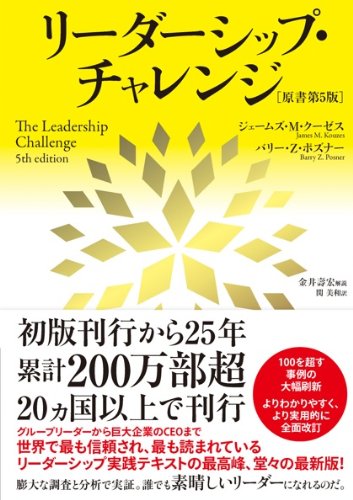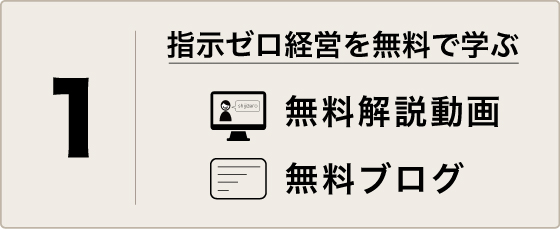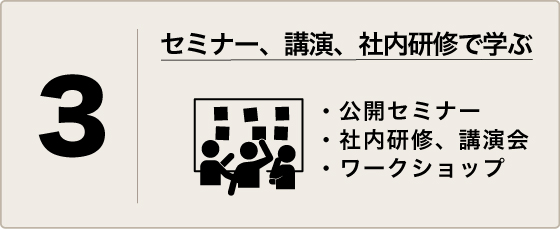後継社長が、先代が創った組織を超えるたった1つの方法
後継社長にとって最初の試練は「自分の組織」をつくることだと思います。
先代が育てた社員たちからボンボン扱いをされることが多く、その状態から実績と信頼を積み重ねていかねばなりません。
リーダーシップの名著に「リーダーシップ・チャレンジ」がありますが、著者のジム・クーゼスとバリー・ポスナーは、世界中のリーダーを調べた結果、リーダーシップの発揮において最も重要な要件は「人間としての信頼」であると言い切っています。
そして、信頼を獲得する上で鍵を握るのが、他の社員への影響力を持つ番頭の存在です。
社員たちは、自分たちの代表である番頭を見て自分のスタンスを決めるからです。
しかし、世の中、多くの後継社長が番頭と上手い関係をつくることに苦戦しています。
なぜでしょうか。
そこにはいかんともしがたいジレンマがあります。
後継社長は、自分の代で経営を進化させたいと願うものです。しかし、新しい取り組みには、良くも悪くも過去の否定というニュアンスが含まれます。
特に3代目はその宿命を負います。2代目は、初代の手法の延長線上で会社を伸ばすことができますが、3代目はその手法が限界に達した時に就任することが多いのです。
過去を否定すれば、それを先代と一緒に作ってきた番頭は自分が否定されたと受け取ります。
だから新社長の方針に反対するのです。
しかし、その本意は、否定されることへの抵抗であり、新社長の方針に反対しているとは限りません。
後継社長にとっては、ここが正念場で、番頭を味方につけることができれば自分の組織づくりに勢いがつきますし、失敗すれば、番頭派と社長派の派閥ができる危険性があります。
どうすれば後継社長は番頭を味方につけ、自分の組織を作り上げることができるでしょうか。
それは、今の会社があるのは先人たちのお陰であることを認識するしかありません。
今、会社が存在するのは過去の選択が正しかった証です。
それを認識せずに新しいことに取り組むから、過去を否定されたと思われてしまうのです。
2009年にヒットしたドラマ「JINー仁」は、大沢たかお氏が演じる医師、南方 仁が、江戸時代にタイムスリップしてしまうという物語なのですが、江戸時代には、麻酔や点滴など、現代医療では当たり前のものが何一つなく苦労します。
南方は、自分がいかに先代の恩恵を受けていたかを思い知るのですが、この気付きが後継社長にも必要性だと思います。
ある若手社長は、自分の代になった際に、トヨタ自動車の伝統車「クラウン」の古いCMを古参社員と一緒に観ました。その昔、クラウンは「いつかはクラウン」というキャッチコピーで、自動車オーナーの憧れの象徴でした。
それから時代は進み、2000年代に入り「ゼロクラウン」が発売になったのですが、そのキャッチコピーが秀逸です。
「かつてゴールだったクルマがスタートになる」
かつて、先代たちがゴールとした地点に立ち、改めてこれまでの功績を感謝しつつ、一緒に新しいスタートを切る決意を伝えるためにゼロクラウンのCMを活用したのです。
ゼロには「無」と「起算点」の2つの意味があります。
後継社長は、先人の恩を無にせず、礎を起算点として未来を描くことを忘れてはいけないと思います。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。