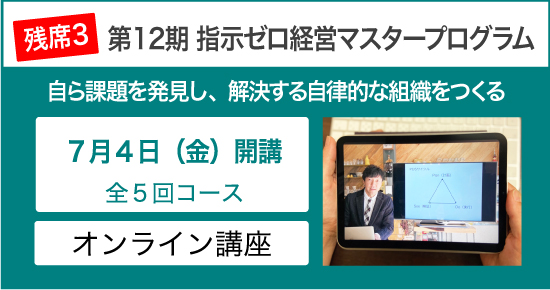不正やルール違反の原因は、社員ではなく「そうさせた仕組み」にある
企業で不祥事が起きると、必ずと言ってよいほど「従業員の教育を徹底します」という言葉が出ますね。
最近では、郵便物の認証事務で偽装が発覚した日本郵政が「今回の事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底してまいります」と発表しました。
また、障がいのある利用客に対し、担当社員が「障がい者のくせに調子に乗るな」というメッセージを送っていたMKタクシーでは「社員教育が不十分であったことを深く反省し、再発防止と社員教育の徹底に取り組んでまいります」とコメントしています。
あたかも「不正の原因は従業員」といった態度なのですが、組織論の視点からすれば完全に「No」です。
人は動機がなければ行動しません。不正には、発覚した時のリスクが伴いますし、不正の立案には相当な思考力が必要ですので、相当な事情がなければやるわけがありません。
不正は「そうせざるを得ない事情があった」ということを疑うべきです。そして、その事情を作っているのは他でもない、自社の組織風土と評価制度であつことが多いのです。
このことは、経営支援を生業としているコンサルタントには馴染みのある感覚だと思います。
現場社員の研修の依頼を受けた時に、真っ先に「抱えている課題は現場社員をトレーニングすれば解決するのか?」と疑いの目を目を向けます。
実際に、現場の課題ではないケースが多いのです。
例えば、自発性の欠如に悩む組織の場合、真の原因は社員ではなく、自発性の芽を摘む組織風土にあることがほとんどです。ある企業では、失敗を叱責される文化があるため、社員は自分で考えずに常に上司の指示を仰ぎます。失敗した時に、上司のせいにできるからです。
「助け合いが起きない」という相談を受けた時には「相対評価を基にした人事制度」を疑います。
相対評価は、S・A・B・C・Dといったランクで社員を評価します。S評価は全体の5%、A評価は10%、Bは40%などと分布を決め、賞与などの原資の分配に差をつけます。
当然、競争原理が働きます。
この制度下では、仲間の評価が上がると相対的に自分の評価が下がる可能性があるので、仲間を助けなくなります。そればかりか、仲間がコケると自分の評価が上がるので、仲間の失敗を喜ぶという殺伐とした職場になることもあります。
評価指標が真因というケースもあります。
例えば、外科医の評価指標を「手術の成功率」と設定すれば、当然、医師はリスクの高い手術を避けるようになります。
ある通販会社では、お試しセットの受注数を評価指標にしたら、受注を増やすために「お試しセットをお申し込みされたお客様の中からカニをプレゼント」という企画を立てました。結果、商品ではなくカニに関心のある顧客ばかり集めてしまい、その後の販促に支障をきたしました。
いかがでしょうか。
問題が表面化した時、つい“人”に原因を求めてしまいますが、優れた組織は“風土”と“評価方法”に目を向けます。望ましくない行動の裏には、そうせざるを得ない制度や風土があるものです。
真の改善は「構造を問う姿勢」から始まると考えています。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
【残席3】指示ゼロ経営マスタープログラム12期
――指示ゼロ経営を学べる唯一の公開セミナーです。――
・自発的に共創するチームワークの条件
・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方
・全員参加のプロジェクトの組み立て方
・自律型組織特有の部下との接し方
・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み
自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。
↓詳細は下のバナーから。