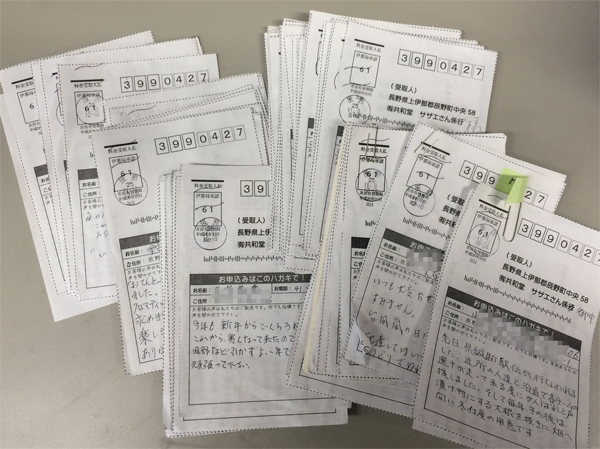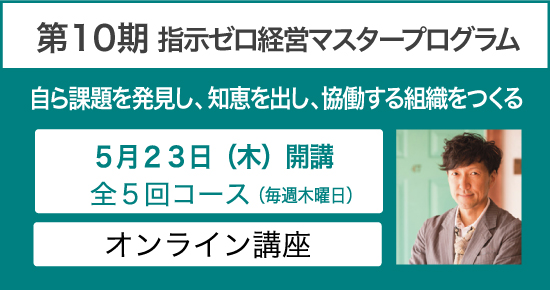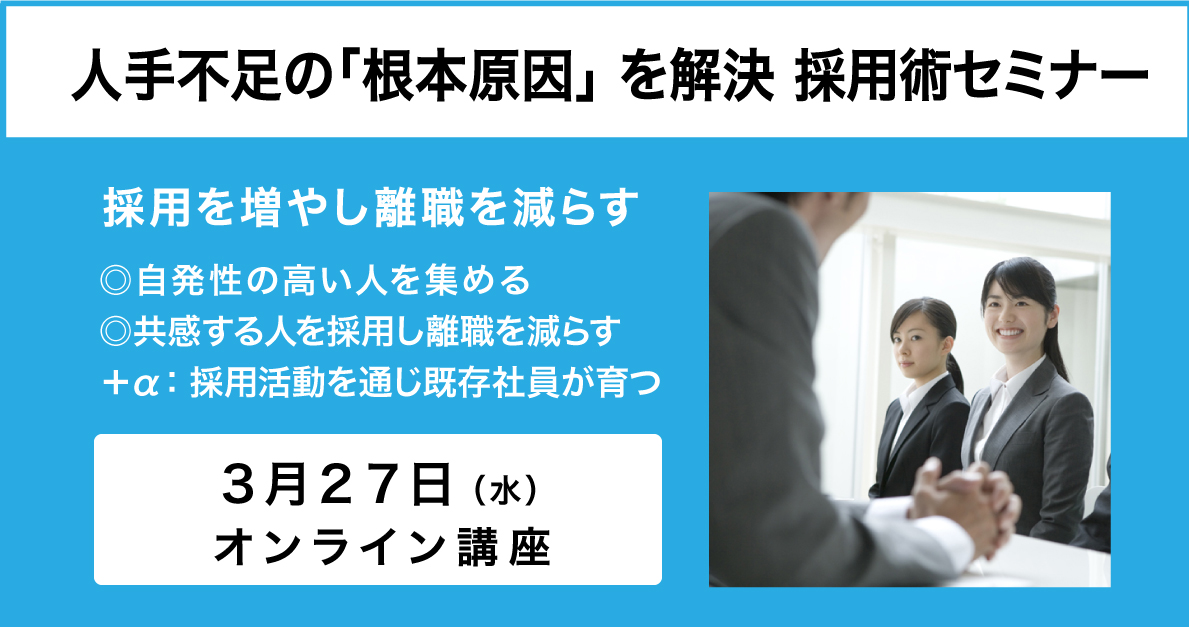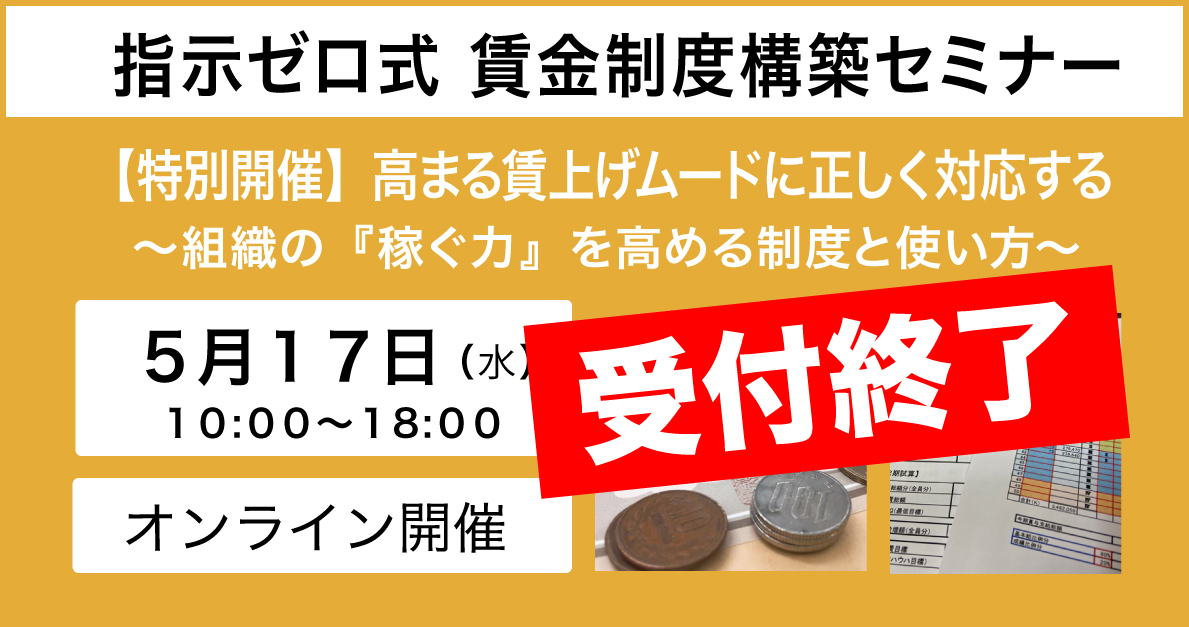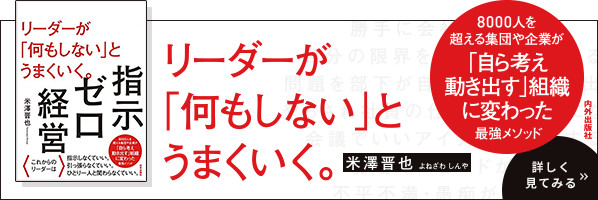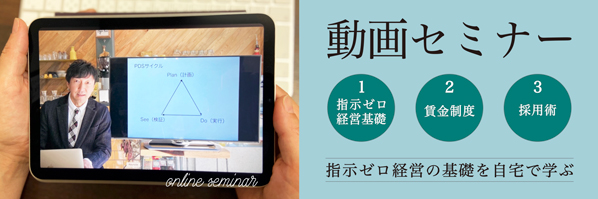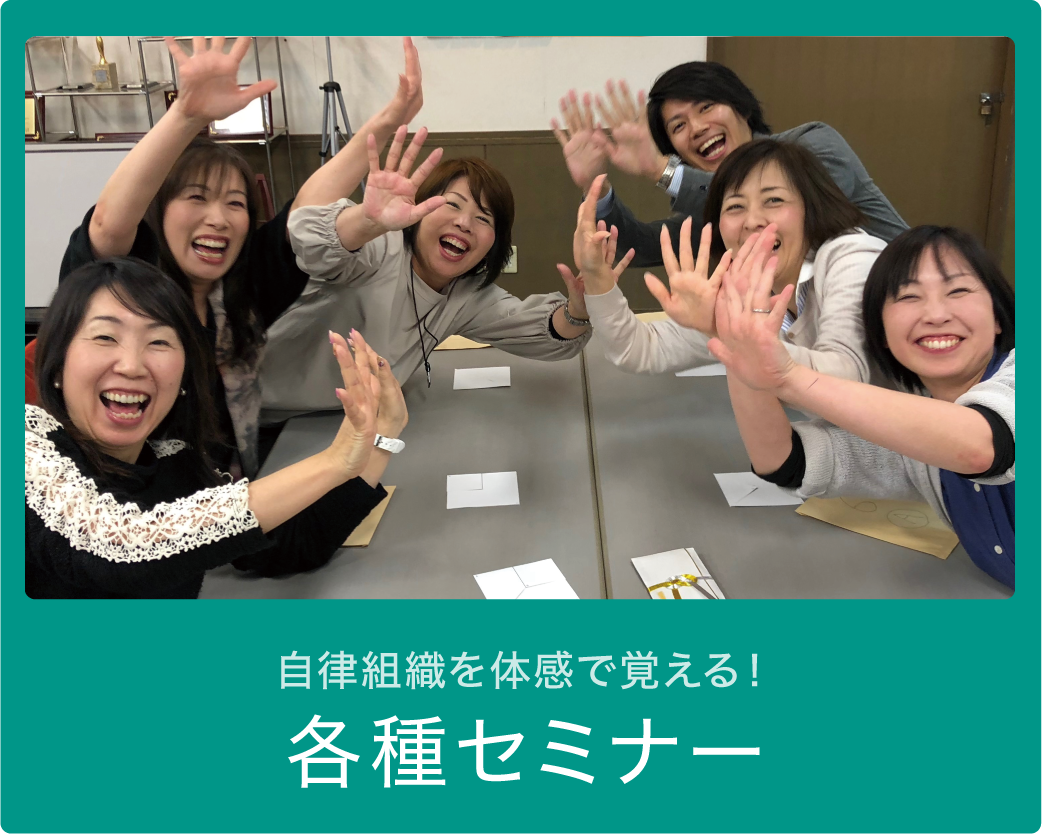全国有数の顧客満足度と働き甲斐を誇る企業の秘訣は情報開示にあった
正しく客観的な情報の開示なしに人もチームも育たない
社員に自発性が足りないと思った時は、社員を嘆く前に「正しい情報がないからでは?」と疑うことです。
人は情報がないと自ら判断し行動することができないからです。
新型コロナの感染拡大を防ぐためには1人1人の心がけが大切だと言われますが、ある人は「Go Toが第3波の原因だ」というし、そうではないと言う専門家もいます。
これでは自主的な判断はできません。
十分な調査ができていないうちに憶測で発言すると混乱します。
しかし、同じようなことが企業でも起きていると思います。
決算書を開示せず「このままではウチは倒産してしまう」と言ったり、リーダーが遭遇した、たった1つのクレームで大騒ぎしたり…
これでは現場は自発的に動くことはできませんよね。
「正しく客観的な情報の開示」…これなしに人もチームも育ちません。
とは言っても、決算書の公開を躊躇する社長も多くいます。
公開してしまえばどうってことはないのですがね。
もし躊躇するのなら、まずはお客様の評価を集め公開することから始めるのが良いと思います。
それを上手にやっている企業さんがあります。
その会社は、僕が委員を務めるホワイト企業大賞に応募された企業さん、「H社」です。
10店舗ほどを展開するサービス業で、全国でも顧客満足度が高い企業です。
また、社員さんが高い働き甲斐を持っています。
全員参加で現状を分析しアイデアを出し実行する
同社では顧客満足調査を年に4回も行っています。
その意図と使い道が素晴らしい。
時々、社員の賞与などの査定のために使う企業がありますが、これでは人は育ちません。
同社では調査結果を店舗に渡し、自分たちで分析、改善が必要な場合は対策を立ててもらっています。
お客様の評価は絶対です。
上司の評価の場合、上司が部下を正しく評価できていないことがありますが、お客様はそうではない。
もし、自社の価値を正しく評価してくれていない場合でも、価値を伝えない自分たちの責任です。
さて、同社では調査結果を店舗のメンバー全員でチェックします。
よく、店長に渡して店長だけが1人で対策に苦慮するケースがありますが、同社では…
1、全員でチェックし
2、全員参加でアイデアを出して
3、みんなで協力して実行します
例えば、お客様から「お店の雰囲気が暗い」という声をいただきました。
そこで全員で元気の良い対応を考えます。
「お客様が入店したらすぐに挨拶をする」「挨拶では通常よりトーンの高い声を出す」など、具体的なアイデアを出し実行します。
実行したら常に全員でチェックします。
改善点がある場合は全員でアイデアを出し、再び実行します。
ここでいう「全員」とは文字通り全員で、接客に直接関係のない経理のスタッフまでもが参画しているのです。
全員が参画する理由は、「自分には関係ない」という人をつくらないためです。
仕事は連携で成り立っています。
連携でお客様の満足がつくられ収益が生まれる…だから自分の仕事ができても仲間ができていなかったら全体として成果は上がりません。
自分だけという部分最適に陥るのを防ぐのです。
同社の社長に「スタッフを怒ることなんてないでしょう?」と聞いたら、「怒る必要がない」とおっしゃっていました。
客観的な情報をもとに、自分たちで課題を見つけ、みんなでアイデアを出し実行し、その結果を再び情報として受け取るわけですから、怒る必要なんてないわけです。
自分たちで考えたアイデアがヒットし満足度が上がった時の喜びは格別です。
これが同社の高い働き甲斐の要因なのです。
人が自発的に動くためには客観的な情報が必要。
スタッフが判断できるだけの情報が開示されているチェックしてみてはいかがでしょうか?
それでは今日も素敵な1日を!
【現在受付中のセミナー】
下のバナーをクリックしてね!