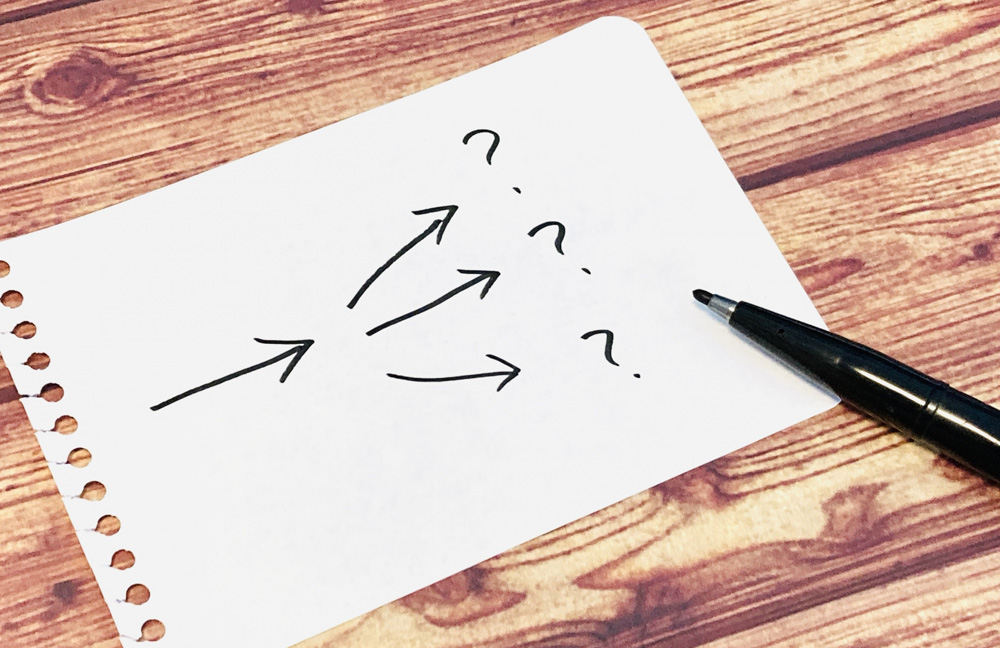成長か衰退か?企業の運命を分ける「節目」の舵取り
人生も経営も、危機は「節目」に訪れます。
その典型が、商品やビジネスモデルのライフサイクルの節目です。商品にもビジネスにも寿命があり、そこでの対応で存続か衰退かが決まります。
前回、「危機を乗り越える秘訣は『手放す技術』にあり」という記事で紹介しましたが、例えば、富士フィルムは、フィルム式カメラが衰退期に入る前に、フィルムで培った「酸化技術」を美容分野に転用し再起を図りました。
節目は企業にとって、存続と衰退を分ける重要な分かれ道です。
→前回記事はこちら
前回の記事では、節目を乗り越えるためには「手放すべき時に手放すべきを手放す」ことが大切と書きました。
富士フィルムは、節目においてフィルム事業を手放すという英断をしたというわけです。
今日は、節目において手放すべき、もう1つの要件「意思決定」について考えます。
意思決定には次の7つがあります。
「何をやるか」「なぜやるか」「どんな出来栄えでやるか」「どの様にやるか」「誰が(誰と)やるか」「いつまでにやるか」「いくらでやるか(予算)」
節目では、この7つの「どれを手放し、どれを手放してはいけないか?」の選択が生命線となります。
まず、どんな節目においても経営者が手放してはいけないものが「何をやるか」「なぜやるか」です。なぜならば、この2つは企業の存在意義を示すものだからです。
経営理念には「◯◯の技術をもって社会の発展に貢献する」といったものが多いのですが、まさに「何を」「なぜやるか」という構造になっていますね。
その上で、節目において手放すものと、手放してはいけないものを整理します。
「変革期」
創業期・ビジネスの転換期など、いわばビジネスを”離陸”させる変革期では、希少な資金が尽きる前に、一気に事業を離陸させる必要があるので、7つ全てをリーダーが独断で決める方が上手くいきます。
意思決定を分散させると、迷っている時間が増え、そうこうしているうちに資金がショートしてしまう可能性があります。
事業の立ち上げを飛行機の離陸で例えましたが、離陸時にコックピット内で、あれやこれや議論している飛行機には乗りたくないですよね。
1つ補足しますと、全ての実務をリーダー1人でやるわけではないということです。意思決定の中に「誰が」という項目がありますので、適切に仕事を振り分けることも大切だと思います。
「安定運営期」
離陸に成功した後は、少しずつ意思決定を手放していく必要があります。その理由は「多様な目」があった方が墜落の可能性が減るからです。
航空機事故の調査統計によると、航空事故は、機長が操縦している時の方が事故発生率が高いことが分かっています。
ベテランなのになぜでしょうか?
パイロットの世界は上下関係の規律が厳しく、副操縦士が機長に対し物申すことは難しいため、機長が間違った判断をしても指摘できないことが事故に繋がると言います。
意思決定の譲り方には2種類があります。
・参画型
・一任型
まずは「参画型」に関して。
リーダーの立場だから観えることや分かることがありますよね。そういう事に関しては、まずはリーダーが提案し、それをもとにメンバーと対話するという方法です。
例えば「どんな出来栄えでやるか」「いつまでにやるか」「いくらでやるか」といった要件に関しては、リーダーから「私はこう考えるが皆さんはどう思うか?」と問いを投げかけ対話をします。
対話を重ねるうちに、やがてそれらを自分事と捉えるようになるでしょう。
「一任型」に関しては、例えば、「どのようにやるか?」「誰とやるか?」といった、現場の方が事情に詳しい案件です。それをやる実力があるということが条件になりますが、丸投げしてしまう方が上手くいきます。
このように、「①どんな時も手放さない事」「②参画型」「③一任型」という視点で整理をすると、意思決定を手放しやすくなります。
節目は、単なる通過点ではなく、危機と繁栄の分かれ道です。何を握り続け、何を手放すかで分かれ道の先の風景が変わります。
その判断基準として今日の情報を活用していただければ幸いです。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ
■社内研修のご依頼はこちら
みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。御社オリジナルの研修を構築します。
現在、2026年1月からの研修を受け付けております。
■講演会を開催したい方
所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!
・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。
・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。