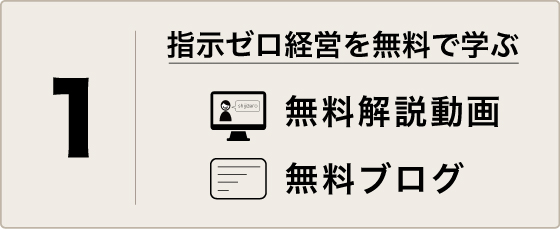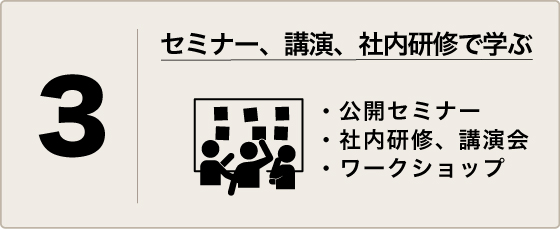実例で考える。対話を怠る組織が「静かなる崩壊」を起こす理由
「敷居が高い」という言葉は「不義理をしてしまい、行きにくい」という意味ですが、最近では「高級すぎて入りにくい」という誤った解釈する人が多いようようです。
ちゃんと関係を結んでおかないと、その後の人間関係に支障をきたすという意味では、職場における対話も同様に「敷居が高い」と言えるでしょう。
対話をサボったら、その後ますます対話が億劫になってしまったという経験はないでしょうか。
対話とは、互いの立場や意見の違いを理解し、ズレを擦り合わせるために行います。非常にエネルギーが要るので、つい避けてしまうんですよね。
しかし、対話をしないとズレは大きくなる一方で、気付くと「今さら対話が出来ない」という関係不全に陥ります。
対話の重要性は、特に近年になり高まっています。
以前、リーダーに求められる能力として「説得力」がありました。その背景には、強いリーダーシップが求められたことがあります。
植木等の代表作「だまって俺について来い」がヒットしたのは1964年のことで、日本は高度経済成長期真っ只中にありました。
勢いよく人々を牽引するリーダーシップが時代に合っていたということで、当時のリスナーの心に刺さったのだと思います。
しかし、今、このタイトルを聞くと違和感を感じる人が多いのではないでしょうか。
時代が変わり、説得よりも「納得」さらには「共感」が求められる時代になり、対話の重要性が高まっています。
対話は運動や掃除と同じで、「サボれサボるほど億劫になる」という性質があります。逆に、マメにやれば、なんてことはありません。
管理職になりたがらない人が増えている現状を受け「AI上司サービス」を提供する会社があると、NHKの「クローズアップ現代」で紹介されていました。
メンバーが自分の活動報告をウェブ上のシステムにあげると、AIが分析し課題を浮き彫りにしてくれるのです。
番組の中で印象的だったシーンがあります。
ある部下の日報に「行けたら行く」という表現が増えたことをAIがキャッチしました。これまで蓄積したデータから、この表現が増えると離職リスクが高まる傾向があるというのです。
番組では、ユーザー企業が、AIの提案もとに上司と部下が対話をしたところ、部下は「機会を作って行く」という、前向きな意味で書いたようで、リスクは杞憂に終わりました。
AIの診断は外れたわけですが、担当者は、AI上司に対し、正確な提案よりも「対話の機会」を与えてくれることに感謝していると述べていました。
僕は数多くの企業の現場で、様々な課題を見てきましたが、起きる問題を遡ると、ほとんどが対話の怠りに起因しています。火種が小さなうちに対話すれば事は大きくならなかったというケースがほとんどです。
例えば、社長と部長の対話が足りないケースがありました。
合意形成が成されないまま仕事を進めたために、社長と部長で方向性が違うということが起きてしまいました。
当然、司令塔が2つできるので、部下は混乱し不満を抱えることになります。すると社長も部長も、自分が嫌われたくないので部下を味方につけようとし、最終的に派閥が出来上がりました。
こうなると、社長と部長の対話はさらに難しくなるという悪循環に陥ります。
暴露すると、僕にも対話を怠った経験があります。
ある社員との対話を「忙しいから」という理由で怠ったことで、社員が悩みを相談できずに1人で抱え込んでしまったことがありました。
放置すればするほど対話が怖くなります。長い時間が過ぎたある日、溜まったストレスが爆発。その社員は退職してしまいました。
組織は生命体ですので、非常に「動的」です。
常に好循環に動いているか、悪循環に動いてるか、どちらかに向かって静かに揺れ動いています。
対話とは、悪循環に陥ることを防ぐためのメンテナンスなのです。
繰り返しになりますが、対話には「サボれサボるほど億劫になる」という性質があります。
対話のスケジュールを決め、ルーティンにすることで悪循環への転落を防ぐことができるはずです。
エネルギーは要りますが、組織は常に動的だからこそ、対話は止めてはいけないと思うのです。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。