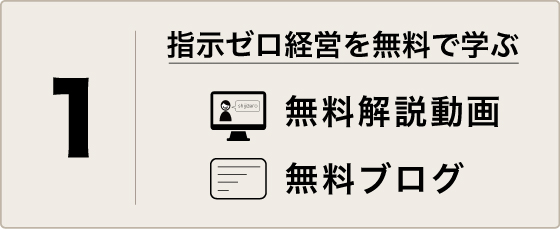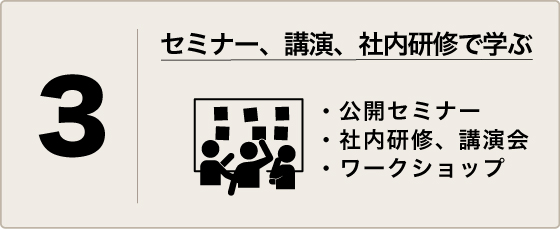「会社は社長の器以上に大きくならない」を科学する
「会社は社長の器以上に大きくならない」という言葉があります。
誰が言ったか知りませんが、僕は多くの企業に接してきて、この言葉は真理だと思っています。
もちろん企業価値は規模だけでは測れませんが、経営者の器と企業規模の間に相関関係があることは間違いありません。
ところが「器」というものが分かりづらい。
小学館が運営する情報サイト「Domani」で調べたら次のように示されていました。
「器の大きい人とは、小さいことをいちいち気にせず、心が広い人のことです。滅多なことでは、怒りや悲しみなどの感情を表に出しません」
どうもしっくり来ませんね。
心が広いというのは分かりますが、「感情を表に出さない」というのは逆ではないかと思うのです。
僕が知る優れた経営者はみんな、理不尽に対しては怒りますし、悲しみを隠さず泣く人が多い。
それよりも、器の要件は「自分が完全ではないことを知っており、他者の言葉に耳を傾けることができる人」ではないかと思うのです。
僕は、自分が主宰するワークショップで、小学生からシニアまで幅広い世代と接して来ましたが、その中で人間は加齢とともに精神的な成熟度が増していくということに気付きました。
1、幼児は衝動的で、気に入らないことがあると感情的になる。
2、小学低学年は大人に従順。
3、思春期〜青年期は自分の意思や考えで行動する。同時に、エゴが強く他者と衝突することもある。
4、壮年期〜老年期は、自分の意思を持ちつつも他者の意見に耳を傾けることができる。
成人発達理論に近い枠組みですね。
もちろん、年齢はあくまで傾向に過ぎません。
この発達プロセスから社長の器を考察すると、非常に有効な洞察を得ることができます。
2の社員と3の社長は相性が良い。
2と3の組み合わせでは、強力なリーダーに従順な社員が依存するという構図が出来上がります。リーダーは権力を維持するために人事権などを独占し組織をコントロールします。組織統制の論理は「掌握」です。
また、2の社員と1の社長が組み合わさると、組織統制の論理は「恐怖」になります。
これらには、共感や信頼、相互理解といった文化はありません。
いずれもリーダーの限界が組織の限界を決めることになります。
また、人望がない人がリーダーに就くと、組織を統制する手段は、より大きな恐怖とより強い掌握しかなくなり、さらに人望を失うことになります。
4のフェーズに入ると、他者の知恵を組織推進のエネルギーに集約することができるので、会社を大きくすることができます。
どうすればこの段階に進むことができるのでしょうか。
明確な答えはありませんが、自分が完全ではないことを知るような出来事…事業の失敗だったり、大病を患ったりといった体験しているケースが多いのは事実です。
精神的なステージアップのためには、まずは、自分が1〜4の、どの段階にいるかを知ることが大切だと思います。
特に3の段階にいるという自覚があれば、身に降りかかる出来事に意味付けをすることができるからです。
3の段階では人間関係にも、自分の精神や肉体にも大きな負荷がかかり、何らかの出来事が起きる可能性があります。
できれば痛い思いをせずに成長したいものですが、器が広がるためには成長痛が伴うということなのかもしれません。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。