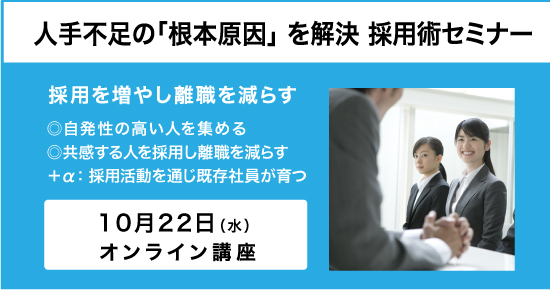人を育てることと組織を育てることは別物…自走型組織育成の2つの鍵
社員1人1人を育てても優れた組織になるわけではないことは、その昔、巨人軍が大枚をはたいて有力選手を集めたのに勝てなかったことからも明らかだと思います。このことは、チームスポーツの経験がある人は納得できるのではないでしょうか。
人を育てることと、組織を育てることは別物ということです。
組織づくりは「関係性の技術」で、それを高める必要があります。
組織で仕事をする際には、次のような要件を、誰かがやらなければなりません。
「問題提起」「指導」「支援」「報連相」「進捗確認と改善」「モチベート」(ヤル気を引き出す)
トップダウン的な組織では、これらをリーダーが一手に引き受けます。
リーダーが優秀であれば優れた組織になりますが、それには相当なコーディネート力が求められます。
先日、NHKのクローズアップ現代で「管理職を救え」という特集が組まれました。調査によると、実に77%もの人が「管理職になりたくない」と答えています。中には「管理職は罰ゲームだ」と言う人もいたとか。
その対策として、番組が紹介していた方法の1つが、まさに指示ゼロ経営でした。
先程の要件を、管理職に依存するのではなく、チームメンバーでこなすという方法です。すなわち状況に応じ、必要な時に、メンバーの中で最も適した人が行うのです。
管理職だけを育てるのではなく、組織を丸ごと育ててしまうという発想です。
そうすることで管理職の負担が減るだけでなく、メンバーに自分事意識が生まれる、変化を自らつくり出すといったメリットがあります。
このような組織を育成するポイントは次の2つです。
1、チームで課題と目標を持つ。
2、リーダーはチームと関わる。
トップダウン組織では、チーム目標はリーダーに課せられます。リーダーは責任を分割して部下に割り当てます。しかし、これでは、部下は自分に割り当てられた領域にしか関心を持ちません。
組織を育てるためには、課題と目標はチーム単位で持つことが大切です。
「皆さんの責任はチーム目標の達成」という大前提を作り、計画をみんなの知恵で作り、役割分担も自分たちで決めます。
リーダーには、メンバー個々ではなく、チームを「1つの生き物」と捉える視点が求められます。
イメージがしづらいち思いますので、具体的な場面をあげて説明しますね。
あるメンバーがリーダーのところに相談に来たとします。
「自分の仕事の進め方で悩んでいまして…」
この場合、リーダーは「それは、まずはメンバーに相談してみて」とチームに返してしまうのが正解です。
この時に個別の相談を行うと、それを見た他のメンバーも個別相談に来るようになり、気づけばトップダウン型に戻ってしまいます。
この話をすると「突き放すのか?」と誤解する人がいますがそうではありません。
メンバーみんなで考えても答えが出せない時は、リーダーもチームの輪に入り一緒に考えます。
ただし、答えは出さずに、上手に問いを投げかけ、自分たちで答えを出せるようにサポートします。
この方法に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
『部下を育てる「!」ではなく「?」のリーダー学』
組織が育つと、リーダーは時間的、精神的なゆとりができますので、会社の未来を考えたり、色んな人に会いに出かけたりと、リーダー本来の仕事ができるようになります。
ただし、組織が育つまでには3年〜5年、場合によっては7年〜10年はかかることを忘れてはいけません。
大切なことは時間がかかるもの。
それを短期間でやろうとすると、組織を疲弊させ、かえって遠回りになります。
というわけで、人材育成と平行して、組織を1つの生命体として捉え育ててみてはいかがでしょうか。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
2025年10月に「採用術セミナー」を開催します。
✓自発性の高い人材がたくさん集まる。
✓面接の時の情熱とヤル気が入社後も続く。
✓指示しなくても自ら考え行動する。
✓先輩社員が新人の教育に関心を持ち共に育つ。