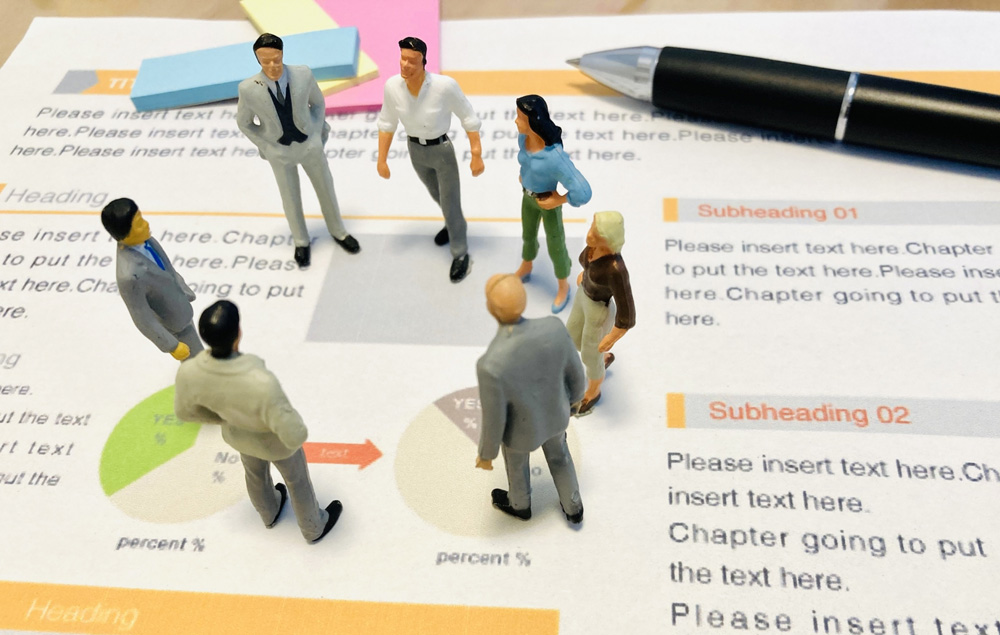リーダーに依存しない。“組織全体で醸し出すリーダーシップ”の可能性
先日、取引先の方から、とても気になるレポートをいただきました。
帝国データバンクが作成した「リーダー人材の不足を企業の69.5%が実感」というタイトルから始まる資料です。
レポートでは、リーダー人材を育てる上での課題として「リーダー職への意欲の欠如」「リーダーシップの欠如」「指導力が未熟」といった要件が上がっていました。

要するに「リーダーになりたがらないし、その実力もない」ということです。
以前より、管理職になりたがらない若年層の増加が問題視されていますね。調査によると「重責を考えると割に合わない」と考える人が多いようです。
私たちは、この問題とどのように向き合えば良いのでしょうか。
それを考える上で確認しておきたいのは日本人の「リーダーに過度に依存する気質」です。
権力に依存する度合いを「権力格差」と言いますが、日本は世界でも格差が大きな国と言います。
権力格差が大きな国や組織では、民(メンバー)は「上の者がしっかりしてくれなければ現状はよくならない」と考えます。当然、組織構造はピラミッド型のヒエラルキー型になります。
対し、権力格差が小さな国や組織では、リーダーとメンバーはフラットな関係にあり、例えば、リーダーが意思決定の際にメンバーに相談をすることを当然と考えます。
メンバーは意思決定に参画した分だけ自分事と捉えますし、当然、自ら考え行動するようになります。
このことは、権力格差と経済力の相関関係を見ると明白です。
権力格差が小さなデンマーク、スイス、オランダ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーといった国々では1人あたりのGDPが高く、いつも国際競争力ランキング上位にランクインしています。
権力格差の違いは、リーダシップのあり方に影響します。
そもそもリーダシップとは関係性を表す言葉です。パートナーシップ、フレンドシップなど「シップ」とつく言葉は「関係性の中で醸し出される現象」を表します。
それが、なぜかリーダシップだけは、リーダーの資質、能力と捉えられているから不思議です。
リーダシップを「所属員みんなの力で醸し出す現象」と捉えている組織では、リーダーだけでなくメンバー1人1人がリーダシップの立役者になります。
僕の経営支援先のある企業では、リーダーはみんなを惹きつけるビジョンを描くことに心血を注ぐ一方で、メンバーは、リーダーに対し助言をしたり、社内に賛同者が増えるように、社長に代わりプレゼンをしたりと積極的にリーダーシップを支えています。
近年では、店長を置かないお店も誕生しています。
組織の自律性が育ったため、ある日「店長って要らないかも」と思うようになり、実験的に店長を置かない店を作ったところ、何の問題もなく業務が回ったのです。
しかも、ルーティン業務だけでなく、突発的な事故対応や事業計画の遂行といった難易度の高い仕事も問題なく進んでいます。
これから、さらに難しい課題に直面する時代に入ります。そんな時代はリーダー依存気質で乗り越えられるほど甘くはありません。
リーダーシップは特定の人物の資質に依存するのではなく、組織全体で育てるべき「資産」です。
権力依存から脱却し、一人ひとりが主体性を発揮する組織こそが、真のリーダーシップを発揮できる組織だと考えます。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ
■社内研修のご依頼はこちら
みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。御社オリジナルの研修を構築します。
現在、2026年1月からの研修を受け付けております。
■講演会を開催したい方
所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!
・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。
・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。