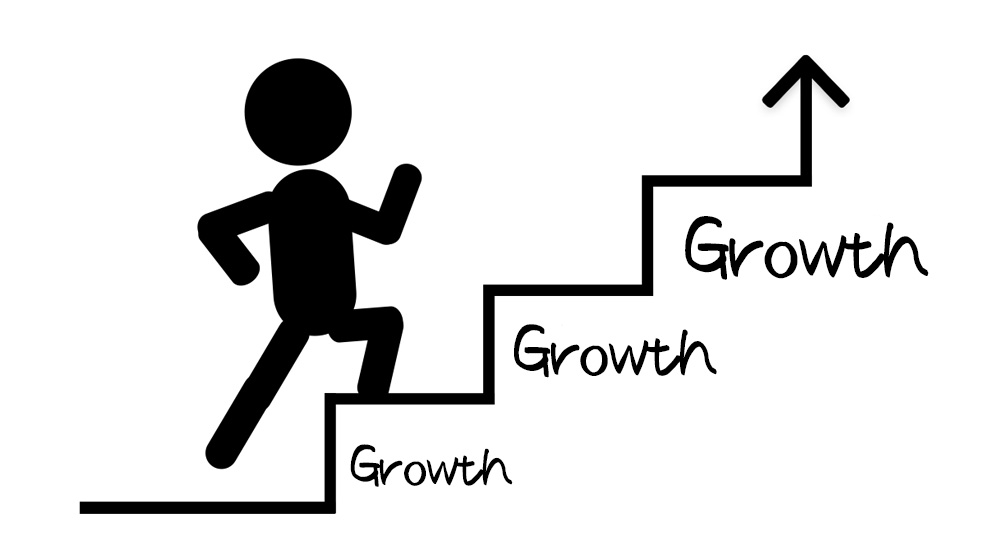人材抜擢の新基準…今の実力よりも「人間的な伸びしろ」を観る
通常、人材を抜擢する基準は「その任務をこなせる実力者」だと思いますが、中長期的な組織成長を考えるなら、違う基準で選ぶ方が良いと考えています。
その基準とは「その任務により、人間的に成長できる人」です。
「ハンカチ理論」をご存知でしょうか。ハンカチの真ん中をつまんで持ち上げれば、吊られて全体が引き上げられるように、人の集団も誰かの成長に周囲がエンパワーメントされ、引き上げられるという考え方です。
この考え方に基づけば、そつなくこなせる人は適役ではないということになります。
話はビジネスから逸れますが、先日、ある方から、ハンカチ理論を実践する小学校の校長を紹介していただきました。
コンフォートゾーンにいる校長の講話は面白くありません。どこかの本に書いてあるような「いい話」をするだけで、校長本人の成長が感じられないからです。
紹介された校長は、一学期の終業式に、児童に「夏休み中に、一輪車に必ず乗ってみせます」と宣言をし、練習を重ねてきました。

結局、夏休み中には満足がいく上達には至りませんでしたが、校長は諦めずに、二学期の始業式で「まだ諦めない」宣言をして練習を継続しました。
少しづつ上達していく校長の姿を見た子どもたちは、非常に勇気づけられているそうです。
ハンカチ効果を狙うなら「伸びしろ」を持った人材を抜擢することですが、そのためには、その素養がある人を見抜く目が必要です。
素養ある人とはどんな人でしょうか。
最大の要件は「失敗を受け入れる度量」だと思います。
成長の第一歩は、自分というシステムが壊れることです。「わかる」というのは「かわる」こと。自分というシステムが壊れ、新しいシステムに変容し、これまでとは違うアウトプットができるようになることです。
伸びしろがある人は、失敗を受け入れることができる、つまり自分のシステムが壊れる痛みを受容できる度量を持った人です。
環境や他人のせいにするのは自己防衛によるものですが、それではコンフォートゾーンから抜け出すことはできませんからね。
以前に、友人から『ラグビー流「人材成長」』という書籍を紹介されました。そこに強いチームをつくる3つの要諦が書かれていましたが、そのうちの1つが「負けから学べるチームを創る」でした。より具体的は「負けを認める」「失敗を認める」ということです。
人材を「今の実力」で選ぶのか、それとも「未来の成長可能性」で選ぶのか…この選択が組織の数年後を決めます。
あなたの会社では、誰を“ハンカチの真ん中”に選びますか?
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ
■社内研修のご依頼はこちら
みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。御社オリジナルの研修を構築します。
現在、2026年1月からの研修を受け付けております。
■講演会を開催したい方
所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!
・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。
・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。