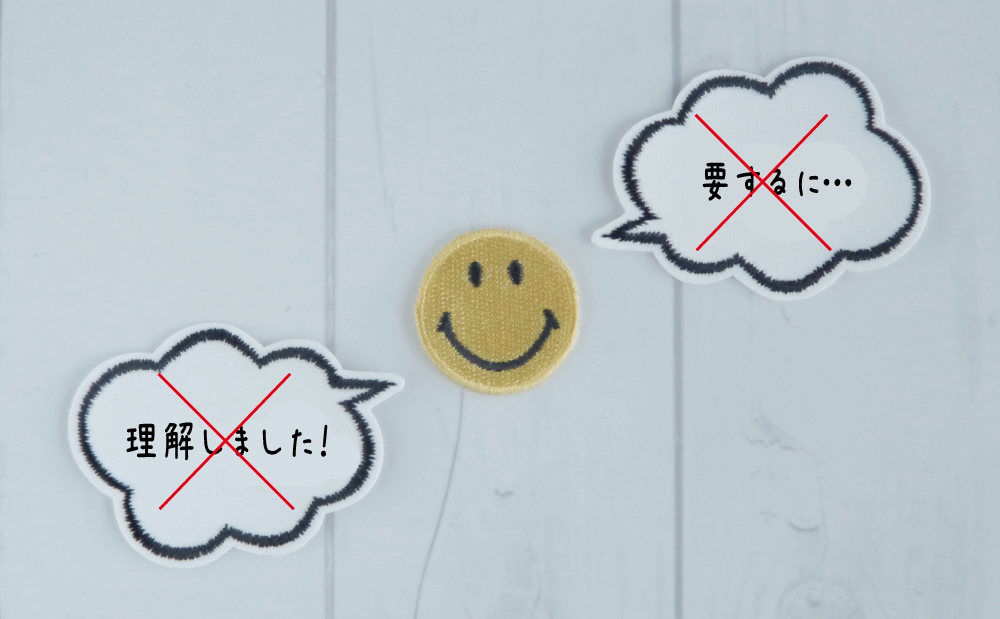学ぶ時は、あえて「馬鹿のふり」をしてみる。
「勉強をした分だけ馬鹿になる」ということがあるようです。、
以前に、とある企業の社員さんと指示ゼロ経営をテーマに交流会を行ったことがあります。
その会社は、誰もが知っている有名企業で、社員さんは本当に頭が良い人ばかりでした。交流会では、指示ゼロ経営に関する質問をたくさん受けましたが、質疑応答の最後に、質問者の多くが決まって同じ言葉で質問を締めるのです。
「理解しました」
「要するに◯◯ということですね」
何度も質問のやり取りをしたわけではなく、一往復のやり取りで、あっさりとこの言葉が出ることに、僕は違和感を覚えました。
そして、その後、僕が伝えた事が、まったく違った解釈をされていたことが分かり驚いたのです。
彼らに何が起きたのでしょうか。
実は、これは「知性の罠」と呼ばれるもので、知識が多く体系化されている人、つまり頭の良い人に多いのです。
どういうことかと言うと、何らかの情報に触れた時に、自分の脳内にある知識と結びつけて「ああ、あの話ね」と「知識の棚」に納めてしまうということです。
斬新な情報の場合、収める棚がないので不快になります。すると、多少、解釈を曲げても強引に棚に収めてしまうことがあるのです。
しかし、それは、思考の枠に収めただけで何のアウトプットも生みません。
買ったCDをろくに聞かずして、ジャンルの棚に収めるような行為です。
アリストテレスは学びには4つの段階があると説きました。
1、分からないことを知らない。
2、分からないことを知っている。
3、知っていることを知っている。
4、知っていることを知らない。
「わかる」は「かわる」ということです。
「わかる」とは、自分というシステムが「かわり」これまでと違ったアウトプットができるようになるということ。そのための第一歩は2に到達することです。簡単に「理解しました」と言う人は、1の段階に留まり続けることになるでしょう。
ところが、人は、ものを考える際に、考える糸口を求めますので「理性の罠」を避けることは難しいと思います。
あなたの組織にもいると思いますし、そもそも自分がそうなっていないか省みる必要があると思います。
僕は件の企業との一件以来、簡単に「理解しました」という人に対し、「それで何が変わりましたか?」と聞くようにしています。
ちなみに、僕の研修は体験ワークを多用しますが、その理由は「理解した」と言っている人が、実は「変わっていなかった」ということに気づく効果があるからです。
賢者の自負がある人ほど「知性の罠」にはまる危険性があります。
そうならないように、学ぶ時は「馬鹿なふり」をしてみてはいかでしょうか。
また、「理解しました」と言う部下には「何が変わったの?」と聞くようにすると良いかもしれません。
最後にお知らせです。
久しぶりに指示ゼロ経営の学習動画をアップデートしました。
指示ゼロ経営の基礎に加え、次のような内容を盛り込みました。
・みんなが「その気」になる。目標を「目的」に昇華する。
・みんなの知恵で事業計画を作る秘訣。
・計画を立てる前にすべき事は「終焉の設定」
・改めて紹介。米澤晋也の失敗体験。
是非、お盆休み中にご覧ください。
価格は5,500円(税込み)購入は下記サイトよりお願いします。
https://shijizero.thebase.in/items/114120177