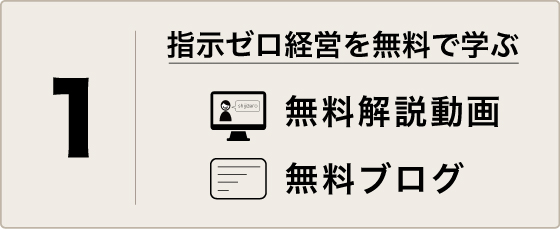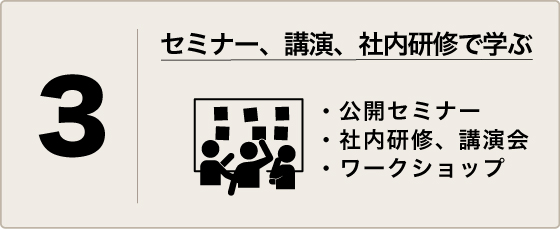最高のリーダーは、時間を経てから部下から感謝される
「今の自分があるのは、あの時の◯◯さんのおかげ」という言葉を聞いたことがあると思います。
「◯◯さん」とは上司や先輩であることが多いのですが、組織を成長させたければ、この言葉が飛び交う組織を目指すとことだと考えています。
この話をすると、「この言葉が飛び交うから会社が良くなるのではなく、良い会社だから、こんな言葉が飛び交うのでは?」と言う方がいますが、そうではありません。
僕は、ホワイト企業大賞の審査員や研修講師を務める中で、この言葉が成長のバロメーターという確信を持つに至りました。
件の言葉は、恩を受けた当時から時間が経ってから聞かれますので、人材育成を長期視点で捉えていることが分かります。また、リーダーは、その当時はそんなに感謝されていない可能性もうかがえます。
人材育成には時間がかかります。
明仁上皇の教育担当を務めた小泉信三は、世界のグローバル化に伴い、産業界の「すぐに役立つ人材を育てて欲しい」という要請に対し「すぐ役に立つことは、すぐ役に立たなくなる」と断ったと言います。
短期間で人を育てることは百害あって一利なしです。
短期間で育てようとするリーダーは「育てるから早く成長して成果を出せ」と、恩着せがましくなります。
こうした恩(恩着せがましい)を受けた部下は、例え相手が嫌な上司であっても、自分に与えてくれる人に対して、返さなければならないというプレッシャー感じます。これは「恩を返そう」という自律的な思いではなく外発的な圧力です。
もし、リーダーの希望通りに育たなかったら、リーダーは部下に対し「困ったやつだ」という態度でプレッシャーをかけるでしょう。
それは、部下には「恩知らずめ」という暗黙のメッセージとして伝わり、部下は罪悪感に苛まれます。
そもそも、短期間で役立つ人材など育たないわけですから、こういうコミュニケーションは、原理的に部下を潰すことになります。
人材育成には「待つ」という能力が求められます。
「今の自分があるのは、あの時の◯◯さんのおかげ」という言葉からは、成長するまで待った「◯◯さん」の存在があります。
きっとその方は、時間がかかっても部下が成長することを信頼していたに違いありません。もしかしたら、自分の思い通りに成長しない可能性も受け入れているかもしれません。
それでも育てるのは、自分もかつて上司や先輩に、そのように育てられたからではないでしょうか。
歴史を振り返ると、偉人の影には「◯◯さん」の存在があります。
アインシュタインは、子どものころ、言語表現が苦手で、お友達と遊ぶのが苦手でした。
単語のスペルを間違えることも多く、語学や歴史などの暗記科目も苦手だったと言います。
エジソンは、少年時代、学校に適応できなかったことで知られています。彼は、好奇心が旺盛すぎて常軌を逸した行動や変な質問ばかりしていたので、小学校を3カ月で辞めさせられました。
そんな彼らを支えたのは母親で、彼らが興味を示すことをとことんやらせてくれたと言います。
東京深川に「ニシザキ工芸株式会社」という、一点ものの高級家具を製造するメーカーがあります。
同社では、社内研修の会場に清澄庭園や美術館を選び、研修後に美術展のチケットを渡し鑑賞の機会を用意しています。
審美眼はすぐに育つものではありません。いかに長期視点で人材育成を考えているかが分かりますよね。
美術展のチケットを渡しても、その時はそんなに感謝はされないかもしれません。
しかし、感謝されないことの積み重ねによって、やがて美意識が開花し、やがて「今の自分があるのは…」と気づくのだと思います。
そして、気付いた時に、後進に同じように接するのだと思います。
時間を経てから感謝されるリーダーは至高だと思うのです。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。