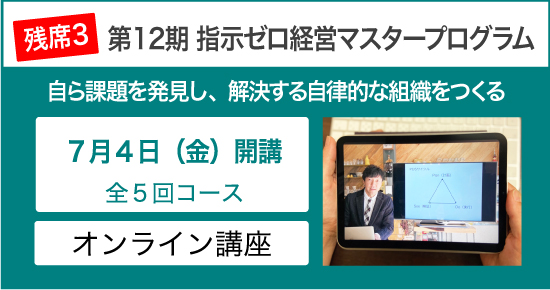中小企業が「小さな日産自動車」にならないために。
日産自動車が6700億円の赤字を計上したと発表しました。
これは「メルセデス・ベンツSクラスを毎日買う」という行為を120年間続けることができる金額です。
う〜ん、目眩がしますね。
実は、中小企業の中にも「小さな日産」が結構あります。
規模の大小の差はあれど、同じような構造で成り立っているのです。
今日の記事では、その正体と弊害、そして防止策を探ります。
日産自動車は大規模なリストラに踏み切ることも発表し、関係者は「やんやわんや」の大騒ぎです。
部品の供給業者や流通業者など、関連企業は19000社にのぼり、一部では「国が救済すべきでは?」という声も上がっているようです。
まるで、思いがけない事態が発生したように騒いでいますが、一部の識者は以前からこうなることを予想していました。
というのも、ひと通りのモノが行き届いた成熟社会では、企業の寡占化が進み、最後には「一強状態」になるからです。
より正確に言うと、便利なモノ=「機能的価値の高いモノ」はそうなる宿命にあります。
コンビニに行くと、文房具や洗剤などの、機能的価値で勝負している商品は、最も支持されている商品が1種類しか置いてありません。
対し、タバコやビールなどの「感性価値」の高い商品は、探すのも大変なくらいラインナップが充実していますね。

自動車産業では、機能的価値が領域はトヨタが総取りし、マツダやスバルなどが感性価値の高い個性的な車で勝負しています。ナンバー1でもオンリー1でもない日産には居場所がないのです。
こうした二極化は街の風景も変えました。
機能的価値の領域はイオンが総取りし、感性価値の領域は小さな店が担うという二極化が進んでいます。
僕の友人は、「買うものが決まっている時はイオンは便利だが、そうでない時は、行っても欲しいものが何も無い」と言います。
機能的価値の商いの特徴を端的に表現していると思います。
機能的価値の領域は「マス」を相手にするので大企業が強く、感性価値の領域は「ニッチ」に対応できる中小企業が強いという傾向があります。
勿論、例外も多くありますが、多くの中小企業が、今後、感性価値に舵を切る必要に迫られると考えます。
感性価値は「量」と相関関係があることが分かっています。
心理学者のディーン・サイモントンは、アーティストや科学者の活動を精査した結果「最も秀逸な成果は、最も活動量が多い時期に生まれている」ということを発見しました。
同時に「その時期には、駄作も数多く生まれている」と言います。
創造性には、偶発性の要素が大きいため「たくさんやってみる」ということが最上の戦略というわけです。
さて、「小さな日産」の話に戻ります。
日産自動車は役職者が多いことで知られています。役員に至っては55人もいるそうで、今回のリストラを機に12人に削減するようです。
役職者が多いと意思決定に時間がかかりますし、稟議を上げていく過程でダメ出しをされる確率も高まります。
つまり、偶発性の芽を積んでしまう構造的欠陥をはらんでいるのです。
中小企業でも、組織活動にリンクしていない役職を設定しているところがあります。
「ちょっと偉い感」を出した部長代理とか。
偶発性こそが感性価値を生む源泉であり、その芽を摘まないフラットな組織こそ、中小企業の強みではないでしょうか。
立場より役割、形式より実行。たくさんの仮説を試し、小さな失敗を繰り返すことで、やがて大きなヒットが生まれると思います。
「小さな日産」にならないために、今こそ組織の在り方を見直すタイミングかもしれません。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
【残席3】指示ゼロ経営マスタープログラム12期
――指示ゼロ経営を学べる唯一の公開セミナーです。――
・自発的に共創するチームワークの条件
・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方
・全員参加のプロジェクトの組み立て方
・自律型組織特有の部下との接し方
・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み
自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。
↓詳細は下のバナーから。