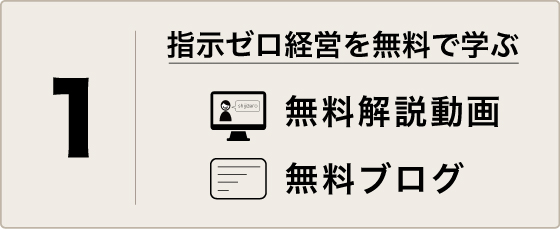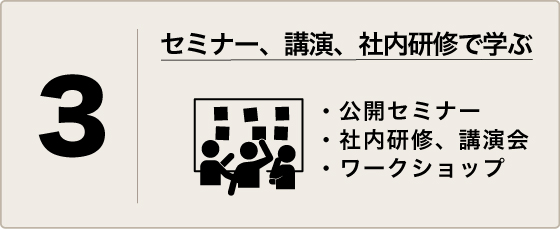良い上司になろうとするほど「悪い上司」と評価される人の特徴
リーダーであれば「良い上司でありたい」と願うものですが、もしかしたら、良い上司になろうとするほどに「悪い上司」への道を突き進んでしまうかもしれません。
どういうことでしょうか。
今日の記事は「良い上司と悪い上司は紙一重」というテーマで、上司にとって最も大切な要件を考えます。
僕の研修では「経験から学ぶ」という手法を活用します。管理職研修では「これまで出会った最高の上司を1人あげ、その人の行動の特徴を抽出し、それを自分にインストールする」というやり方をとっていました。
同時に、反面教師として、これまで出会った「最低の上司」の特徴も挙げ、そうならないように気をつけるというアプローチも取ります。
ある日、面白いことに気づきました。
実は、良い上司と悪い上司の特徴を比較すると紙一重の関係にあるのです。例えば、最高の上司の特徴としてよく挙がる「丁寧に関わってくれる」という特徴と、最悪の上司の特徴で挙がる「細かなことにまで干渉してくる」という具合に。
他にも、「思いっきり任せてくれる」と「丸投げする」も同様ですね。「間違ったことをした時は厳しく指導してくれる」という特徴は、パワハラと紙一重です。
では、何が違うのかというと、これが不明瞭なのです。
実は、これらは「人によって変わる」のです。
同じ行為でも、上司によって、部下の感じ方が変わるのです。
これはハラスメントも同様です。
「髪型変えた?」というひと言が、それを発する人によって「気づく人」にもなれば「セクハラ」にもなります。
あるいは、部下によって感じ方が変わることもある。
つまり「関係性の問題」ということです。
ハラスメントの認定調査が難航する理由はここにあります。関係性という曖昧な要素が大きく影響するので1つの尺度で測りきれないのです。
勿論、殴る、怒鳴る、触る、私生活のセンシティブな事情に踏み込むといった行為は論外ですがね。
僕がやってきた「最高と最低の上司ワーク」はそもそも的外れだったということで、今では、紙一重の関係になっていることに気付くために行っています。
「関係性の問題」ということは、上司だけの問題ではなく、全員で取り組む必要があるということになります。
第7回ホワイト企業大賞で「大賞」を受賞した、有限会社谷川クリーニングでは、全員に関係性向上のリーダーたることを求めます。
例えば、採用面接の時に「小さい子どもがいるんですが、学校行事がある時には早退させてもらえますか?」と聞かれた時に谷川社長はこう答えるそうです。
「私には分かりません、もし、あなたが普段から仲間に貢献していたら、そういう時に仲間は助けてくれるでしょう」
信頼関係がなければ、周りの人は、その人のことを「自分の都合で休む人」と思うでしょうし、当人は、周りに対し「理解がない人たち」というレッテルを貼るでしょう。
関係性は共創の産物なので、どちらか一方だけで築けるものではありません。
関係づくりは全員の責任であり、職場全体のテーマということ。
互いが関係性のリーダーであるという自覚を持つことで「良い上司」「良い部下」を輩出する会社が生まれるのではないでしょうか。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。