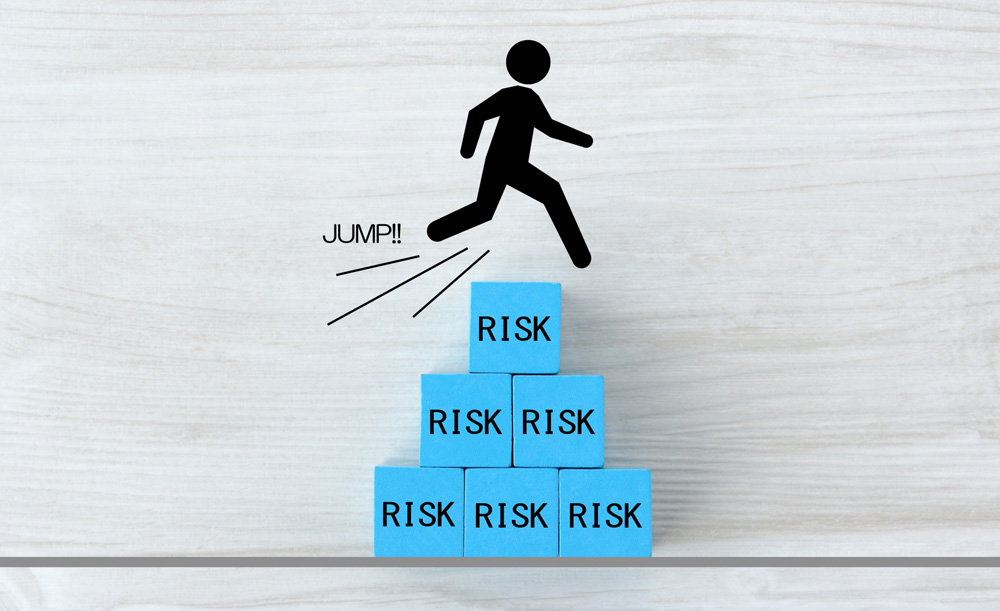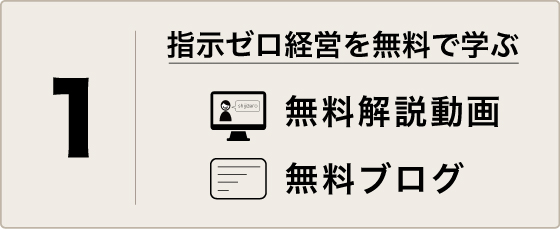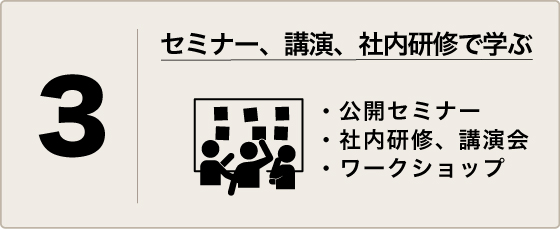それ、ピンチじゃなくチャンスかも。危機が来ると強くなる組織のつくり方
私たちは、強い企業に対し、変化や外圧に直面してもびくともしないというイメージを持っていますが、そのイメージはもう過去のものだと思います。
具体例で説明しますね。
2023年に出した僕2冊目の著書「賃金が上がる!指示ゼロ経営」(通称「青本」)で事例紹介した名和株式会社です。
同社はプロ球団チアの特注コスチューム、アスリートや女性用のスポーツウェアを企画製造しているメーカーです。
2020年、コロナ禍に入り、みんなが集まってのスポーツやイベントができなくなり、既存事業の受注がゼロになりました。
先行きが全く見えない中、社員さんからマスク製造の提案を受けます。
社長が資金繰りで奔走している間に、社員さんが自発的にミーティングを開いていたのです。
同社には優秀なデザイナーがいますし、質の高い素材があります。ただのマスクではなく、小顔効果、保湿効果、着け心地がいい、柄がユニーク、など様々なマスクを発案し、2020年4月に販売を開始。パンデミック発生から約1年間で10万枚以上を販売しました。
この話を最初に聞いた時に、僕は「変化に即応できるんだな」という感想を抱きましたが、よく考えると、もっと上を行っているのです。
それは
「変化や混乱が起きるとかえって強くなる」
というものです。
これが生産システムが完全機械化され、大量生産体制が充実した「頑強な企業」はどうだったでしょうか。
まったく身動きが取れず硬直した企業がほとんどでした。
多くの企業が危機に翻弄される中、同社では危機の中からチャンスを拾ったのです。
このように、変化や外圧の高まりによりパフォーマンスが上がる様態を、リスク・不確実性の研究家であるナシーム・ニコラス・タレブは「反脆弱性」と名付けました。
頑強とは、外圧や過環境変化に強い状態を指します。それらに弱いのが脆弱です。
しかし、タレブ氏は、環境変化や外圧の高まりにより、かえってパフォーマンスが上がるケースを発見したのです。
大切なことなのでもう一度確認しますね。
「変化や外圧に耐える強さではなく、変化や外圧が起きるとかえってパフォーマンスを上げる」ということです。
反脆弱性が注目されるのは、とりも直さず変化の激しさが増している社会環境にあります。
大国の大統領の発言や意思決定で株価が激しく上下しますし、インフルエンサーがInstagramで呟けば、一瞬でトレンドが変わってしまいます。
その様子を見て「変化をつくり出す側は強い」と言う人がいますが、一方で、変化の高まりを機会に変えている組織があるのです。
反脆弱性を高めるためには、組織内に「ランダムな状態」を意図的に作ることです。
その様子は自然界に学ぶことができます。
ミツバチは、蜜を探す時に、個々のハチが四方八方に探索に飛び、蜜を発見したハチが仲間に独特のダンス(八の字ダンス)を踊り報せます。
蟻が、エサを蟻塚に運ぶ最短ルートは、集団行動ができない不良蟻が偶然に発見することが多いと言われています。
ランダム性を高めるためには、言うまでもなく、現場が自ら考え行動する自律性が求められます。
変化は、恐れるものではなく、私たちを進化させる贈り物かもしれません。不確実な時代だからこそ、自ら動き、揺らぎの中で強くしなやかに育つ組織でありたいですね。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。