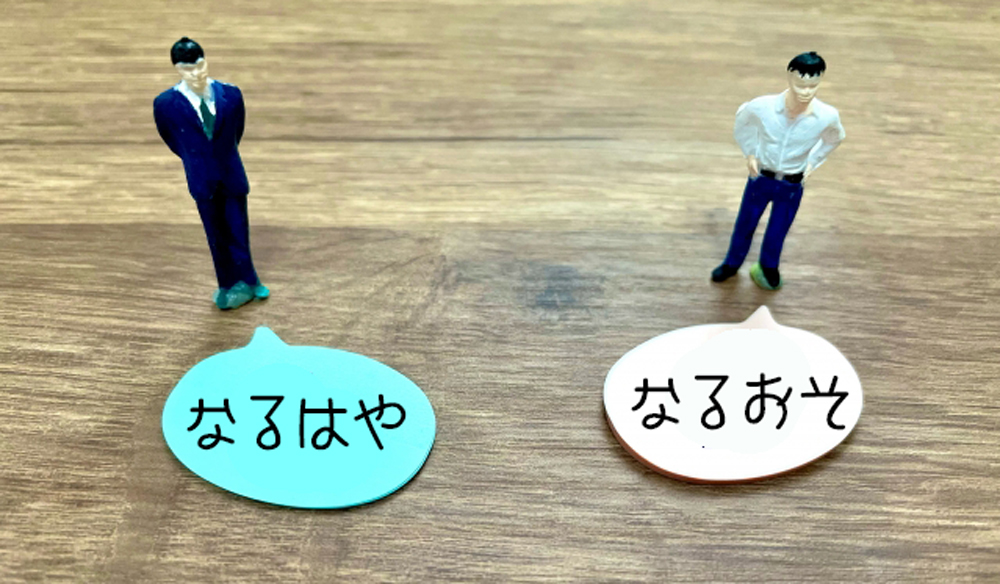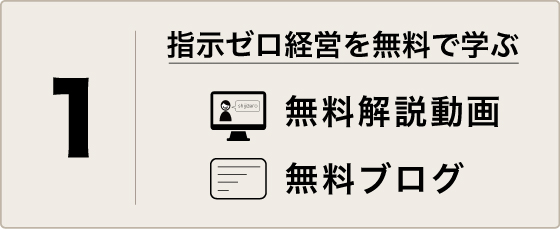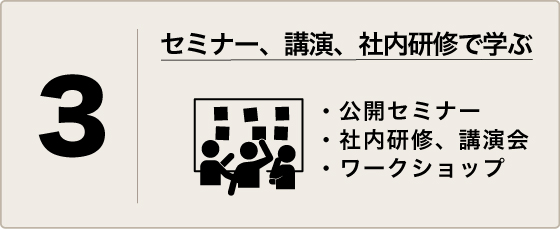「なるはや」から「なるおそ」へ…「待てる」が未来を拓く
「なるはや」とは「なるべく早く」の略称で、ビジネスパーソンにとって重要な考え方とされています。
もともとは、対応に急を要する際に使った言葉だそうですが、スピード重視の現代にマッチしているため、より広い意味で使われるようになりました。
「すぐに実行に移す」
「前倒しで仕事を進める」
「意思決定が早い」
現代人が聞けば称賛の言葉にしか聞こえませんが、はたして100%称賛して良いのでしょうか。
物事の良し悪しは、状況と文脈により変わりますので絶対的なものではありません。
というわけで、今日は「なるはや」の反対である「なるおそ」(なるべく遅く)の価値についても考えたいと思います。
僕は、研修の資料作りは「なるおそ」で取り組むようにしています。その理由は、資料を作った後に新しい情報や知見を知ると、どうしても内容をアップデートしたくなるからです。だから、情報収集をしつつ、ギリギリまで待ち、満を持して資料づくりを行うのです。
これが可能なのは、資料づくりに時間がかからないからです。
すでにパソコンに莫大な量の資料がストックされていて、そこに新しく手にした情報を加え編集するだけなので、3時間もあればできてしまうのです。
寿司屋のように、ネタを取り揃えておいて「残すは最終工程」という状態を作っているのです。
戦略的に「なるおそ」を狙っている企業といえば、トヨタ自動車です。
自動車産業は、カーボンニュートラルのトレンドを受け、内燃エンジンに代わるシステムの開発に心血を注いでいます。
電気自動車市場はテスラが牽引し、BYDやGMがそれを追う形になっています。
一方、トヨタは、電気自動車や水素カーなど、ひと通りの研究開発(準備)はしていますが、積極的な販売はせず、市場の動向を静観しています。
先駆者にはならないが、需要が盛り上がれば、後発から一気に躍り出て市場を制覇する勝ち方ができるからだと思います。
専門家の中には「先駆者にこそアドバンテージがある」と主張する人がいますが、その限りではないことは歴史が証明しています。
ちなみに、僕はそれでも先駆者を支持したいと思っています。理由はシンプルで、先駆者の勇気と哲学をリスペクトしているからです。
僕の好みはともかくとして、準備ができている人は、打って出るベストタイミングまで待てるので機会損失が少なくなります。
他にも、近年、注目されている「ネガティブ・ケイパビリティ」も同様です。
ネガティブ・ケイパビリティとは、人材育成など、すぐには答えの出ない課題に対し、あるいは対処しようのない事態において、待ち耐える能力を指します。
ネガティブ・ケイパビリティがある人は、よほどの胆力の持ち主か、「残すは最終工程」という状態を作り、満を持す人のいずれかだと思いますが、この中で凡人に可能な方法は後者ではないでしょうか。
変化が激しい時代ではスピードが命と言われますが、何でも早く動けば良いというわけではありません。機が熟すまで待つという選択も忘れてはいけないと思うのです。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。