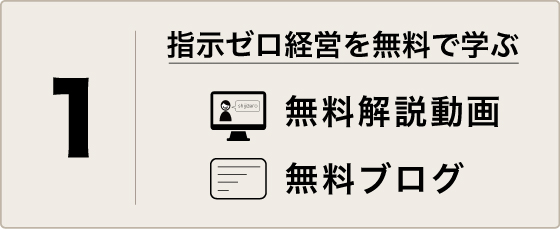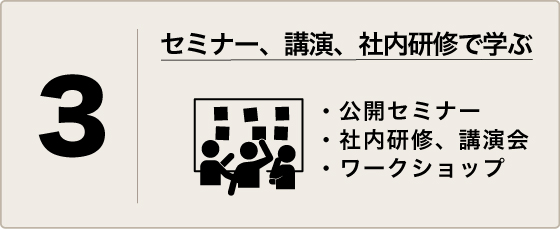部下から指導を受ける勇気はあるか?…AI時代に活躍するリーダーの条件
AIの進化が留まるところを知りません。
最近では、何か相談すると、その先にあるであろう課題まで予測して問題提案をしてくれます。
例えば、「夏の野菜を教えて」と聞くと、回答後に「夏の野菜を使った料理も提案しましょうか?」なんて言ってくる。
経営者なら、このような、気が利く人材を求めているのではないでしょうか。
と思ったのですが、実はそうでもないようです。
先日、友人が「AIは余計な提案をしてきて嫌だ」と文句を言っていました。詳しく聞くと、賢すぎてマウントを取られた感じがするとのこと。
これを聞いて、僕は結構、共感してしまいました。
というのも、以前、社員が僕が知らない知識を使って解決策を提示した時に、同じことを思ったことがあるからです。
頭では優秀な社員を求めていても、感情レベルでは拒絶することがあるのです。
これは、決して特殊なケースではありません。
多かれ少なかれ、リーダーは「部下よりも優れている」と思っていますし「そうあらねばならない」と考えているものです。
これは向上心の源であると同時に、出る杭を打つ原因にもなるので注意が必要です。
社員と議論をしている時、リーダーは「本当のところ」何を感じているでしょうか。
議論の動機が、自分の賢さを示すためになっていないか内観する必要があると思います。
近年「リバースメンタリング」が盛んに提唱されるようになりましたね。
若手社員がメンター(指導者)となり、先輩社員や上司に助言や指導を行う、立場を逆転させた人材育成の手法です。
時々、「私は経験豊富だ」と豪語する年配者を見ますが、今は、これまでの尺度で測ることができない課題が増えているので、経験豊富の価値は日に日に目減りしています。
最新のテクノロジーは勿論、社会の潮流など、経営の骨格を左右するアドバイスにまで踏み込むケースもあるようです。
これは、上司に相当な精神的成熟を要求します。
新しい知識を身につけるよりも、一度、身につけた知識や思考パターンを手放す方が難しいものです。
さて、リバースメンタリングにより精神的な成熟を遂げた人は、どんなリーダーシップを発揮することができるでしょうか。
その典型が「サーヴァントリーダーシップ」です。
サーヴァントとは「召使い」のことで、上司は部下の主体性を信頼し、任せ、自らは支援に徹するマネジメントスタイルです。
デキるリーダーはたくさんいますが、部下をデキる人にしてしまうリーダーはあまりいません。
世の中は、いつも希少なものに価値が付きます。
AIの進化によって、知識を持つ人が過剰になります。知識を身に付けた人は、それを多くの人に披露したくなります。それはすなわち、話を聞いてくれる人の存在が希少になるということです。
ここに「求められるリーダー」の道が観えてくるのではないでしょうか。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。