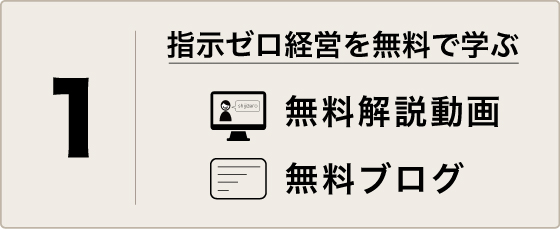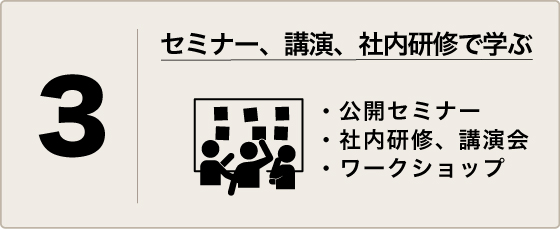人材を「利益の手段」にしない経営
僕は「経営資源」という言葉を、いつも違和感を抱きながら使ってきました。
一般的に経営資源といえば「人」「モノ」「金」「情報」ですが、特に「人」に強い違和感を感じるんですよね。
僕は、社員を目の前にして「君たちは重要な経営資源だ」と言うことができませんでした。
その理由は、人間が「目的のための手段」という位置づけになっていること。さらに言えば「誰かの目的のための手段」という構図を感じるからです。
目的とは、言うまでもなく利益。誰かとは経営者や株主です。
経営資源という言葉が頻繁に使われるようになった背景には、ピーター・ドラッガーの影響が強いと思います。ドラッガーは経営資源をヒト・モノ・カネ・情報と考え、それらを効果的に活用することがマネジメントの目的であると提唱しました。
いかにも戦略家の発想ですが、当時の人たちがこれを支持したのは、経済的な富=幸福と信じて疑わなかったからです。
実際に、経済の発展が人々の幸福度を底上げしたという事実があるわけです。
しかし時代が変わり、経済的な富と幸福度の比例関係が無効化されました。
それに伴い「手段としての人間」という考え方に違和感、率直に言えば嫌悪感を持つ人が増えました。
僕は新聞店の社長を長年やってきました。
新聞配達スタッフの中には、お金を稼ぐために頑張っている人が多くいます。
彼らに「何のために新聞配達をしているのか?」と聞くと「お金のため」と即答します。そこで「稼いだお金は何に使うのか?」と深堀りすると、家族のためや、自分の暮らしを豊かにするためといった「真の理由」が観えてきます。
「何のために?」を突き詰めると、全員が「幸せに生きるため」に行き着くんですよね。
彼らは、幸せな人生のために仕事、会社を活用しているのです。
一方、経営者に「何のために商売をしているのか?」と問うても同じ結論に至ります。
「より良い社会の実現のため」といった利他的な動機を持つ経営者もいますが、それも、それをすることが幸せだからであり、自己犠牲のもとに商売をやっているわけではありません。
つまるところ「人は、幸せのために企業という資源を活用している」ということになります。念のために注書きをすると、企業を「利用」しているのではなく「活用」しているということです。
あたかも、地域の湧き水を地域住民が保全しながら大切に活用するように。
利益は何なのでしょうか?
「幸福のための手段」と捉えることもできますが、僕は違う考え方を持っています。
僕が住む地域に「かんてんぱぱ」で有名な、伊那食品工業株式会社があります。
創業者の塚越 寛さんは「利益はウンチ」と言います。「健全な経営をした結果として利益が出た」という捉え方です。
数々の研究が明らかにしているように、人は、幸福でワクワク活動をしている時に豊かな創造性を発揮します。良い商品を創るし、業務効率も良くなるし、接客も気が利く。結果、利益が出る。
すなわち利益は「現象」なのです。
利益をウンチに言い換えると、世の中が面白く観えます。
「ウンチ創出」「企業の唯一の目的はウンチ」「ウンチ至上主義」「ウンチから逆算する」
健全な活動をしていれば良いウンチが出るのに、排泄に意識が偏れば、ストレスで便秘になってしまいますし、度が過ぎると血便が混じるかもしれません。
利益をウンチと捉えれば、利益は自分たちの健全度を測るバロメーター、つまり検便のようなものでしょうか。
私たちは、そろそろ人間をウンチの手段と捉える思考を変える時期に来ているのではないかと思うのですは、みなさんはどうお考えでしょうか。
朝からすみませんでした。笑
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。