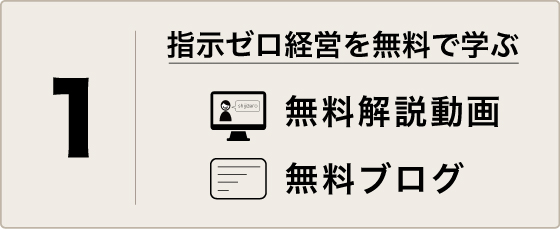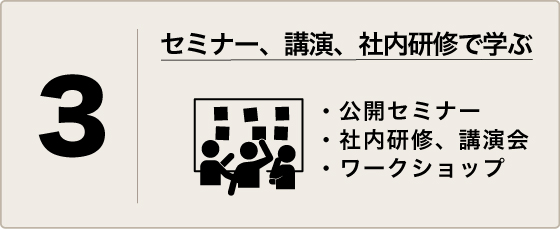組織は変革が求められる時に変革できない
革新的で勢いがあった企業が、気づくと「尖り」をなくし平凡になることがあります。
世間の人は、その姿をみて「丸くなった」「牙を抜かれた」と評論しますが、そもそも組織はそうなるものだと思います。
丸くなるということは成熟したと評価することができますので、それ自体は悪いことではありません。
問題は変革ができなくなることです。
「組織は変革が求められる時に変革できない」…構造的にそうなる宿命を負っています。
どういうことでしょうか。
このことは組織の立ち上げから成熟するまでの過程を見ると分かります。
創業を飛行機の離陸に例えることがありますが、離陸する時は、組織がガタガタと揺れるので強い推進力が必要になります。
創業者には良い意味での独裁性が求められます。
その後、安定飛行に入ると、社員数が増え「マネジメント」という役割が必要になります。
創業メンバーには、多少のリスクがあっても挑戦する根性が求められるのに対し、マネジメントには、リスクを予見し回避策を考える能力が求められます。
まったく違うタイプの人間が、同じ組織に同居しなければならないのです。
構成比率はどうでしょうか。
経験則では、安定飛行には、後者(安定飛行組)の比率が6割以上必要とされています。
後者は、トップの独裁にかき回されることを嫌いますので、組織は自然と民主的になっていきます。
民主的な経営では、みんなに支持された人が管理職に選ばれます。
こうして、組織は丸くなっていくというわけです。
さて、ここで問題が発生します。
安定飛行はいつまでも続かず、やがて新たな挑戦が求められる段階に入ります。
しかし、みんなに選ばれた守り体質の管理職のもとでは大胆な変革に進むことができません。
これが、「組織は変革が求められる時に変革できない」ということです。
これを防止する方法として、3M社が採用している制度が参考になります。
同社には、「試してみよう。なるべく早く」という社是があるように、挑戦し続ける風土づくりに力を入れています。
それを支える制度として、開発職は、勤務時間の15%を通常業務以外の好きなことに使えるそうです。
ただし自由に対しては責任が伴います。
「過去3年以内にリリースした新商品が売上高の一定比率を上回っていなければいけない」というルールを設けているのです。
このくらい徹底しないと、組織の原理上、変革ができないということを示しています。
「変革せよ、さもなくば衰退せよ」とはジャック・ウェルチの言葉ですが、それを阻むのが、まさに組織という存在です。
風土は、みんなの一挙手一投足で出来上がりますので、今日の記事は是非、社員さんと共有してください。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。