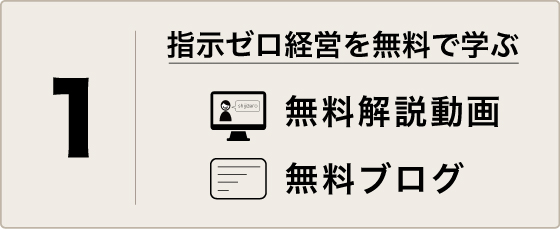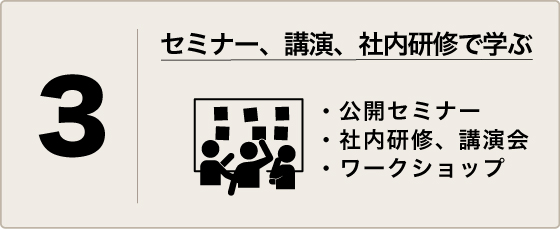「社員を信頼したら騙された」を防ぐ方法
経営の世界には昔から「人と業務を分離する」という考え方があります。
「あの人だからできる」という状態を嫌い、誰がやっても同じ水準のアウトプットを目指してきました。
「個性は不要」と言わんばかりの傲慢な考え方に思えるかもしれませんが、それが求められた時代がありました。
僕が子どもの頃は、製品の品質のバラツキが多く、買って家に帰って箱を開けたらすでに壊れていたという事がありましたからね。
当時の「良い製品」とは、そういうことがない優秀な製品で、それが作れる企業がブランドの冠を手にすることができたのです。
僕が高校生の時、世がバブルに浮かれていた時代にファミレスが急成長しましたが、どの店に行っても笑顔で「いらっしゃいませ。◯◯へようこそ」と挨拶する店員さんを見て感動した覚えがあります。
ところが、こうしたサービスに慣れた生活者が増え、あれほど丁寧だと思った接客は、通り一遍と揶揄されるようになり競争力にはならなくなりました。
そこで、その場と状況に合わせた、オリジナルの「おもてなし」を求める生活者が増え、企業がこぞって学ぶようになりました。
そんな状況下にあり、頭ではそれを求めているが、心では拒否している経営者がいます。
その理由は、人と業務を分離する経営をやめる=人を頼りにする経営になり、権力を維持できなくなる恐れがあるからです。
社員が力を持つことへの拒否感は、時間とともに心の奥底に沈殿し、無自覚のうちに社員の自発性な行動や成長を潰します。
しかし、その恐れは大抵、リーダーが勝手につくり出した疑心暗鬼です。
社員は、権力を経営者から奪おうなどとは思っておらず、仕事を心から愉しみたいだけです。権力争いに発展するのは、互いが疑心暗鬼を持った時で、その第一歩は経営者が社員に疑心暗鬼を向けるところから始まり、やがて疑心暗鬼の応酬に発展するのです。
ほとんどの社員は、充実した仕事ができることに誇りと喜びを感じ、経営者に感謝します。
「ほとんどの社員は」ということは、一部の社員は権力闘争を仕掛けてくる可能性があるということで、その対策は必要です。
最も有効な対策は、そういう社員が現れた時に、周りの社員が賛同せずに止めることです。
このことは、学校で起きるイジメの実証実験で明らかになっています。イジメをなくす鍵は、当事者ではなく周りの人間が握っています。傍観者にならずに止める人が20%〜30%いると、集団内にイジメを止める行動が広がり、クラスからイジメがなくなります。
優れた教師は、こうしたメカニズムを子どもたちと共有し、イジメの芽を摘む協力を求めます。
イジメを止めると自分が標的になる可能性もあるため、教師は「絶対に私が守る」と宣言することが欠かせません。
これと同じ構造を職場で作るのです。
周りの社員には止める動機があります。疑心暗鬼の応酬になったら心理的安全性は破壊され、社員は自分の個性を活かした仕事ができなくなるからです。
疑心暗鬼により組織が崩壊した企業を、僕は何社か知っていますが、一度疑心暗鬼の応酬が始まると回復にはものすごい労力と時間がかかります。
人に依存しない経営からの脱却には、こうした危険性があることを、リーダーだけでなく社員も知っておく必要があると考えています。
是非、今日の記事を活用し、理想の組織について対話するキッカケにしていただければ幸いです。
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。