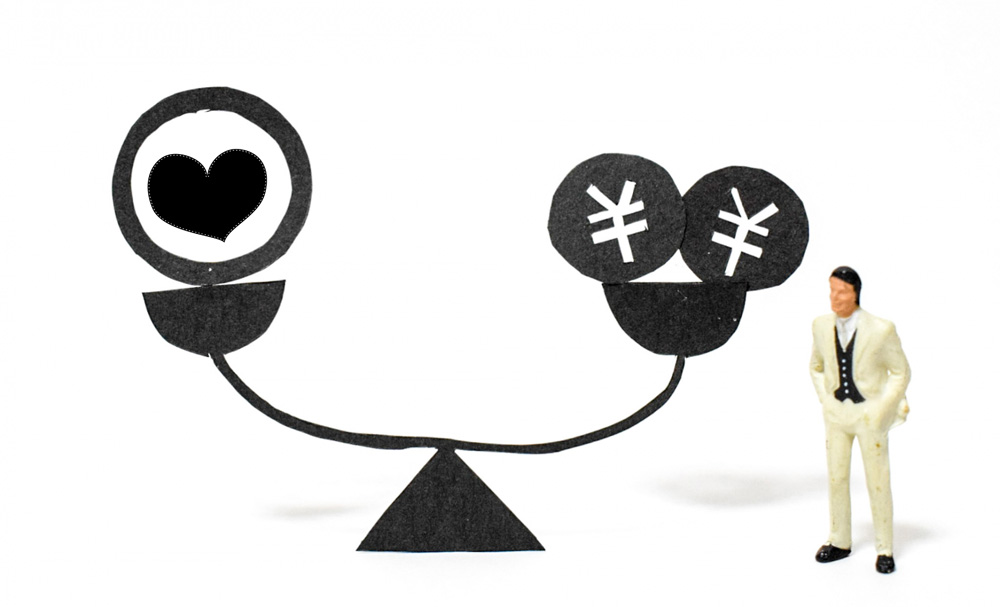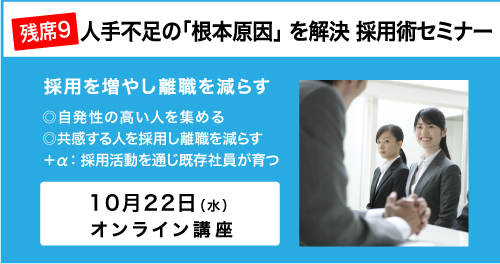逆張りの採用戦略…待遇で勝負する企業を横目に「別の強み」で抜きん出る。
人手不足を受け、企業は様々な対策に乗り出していますが、調べると、どうやらあまり効果的な対策ができていない実態が観えてきます。
日本商工会議所の調査によると、中小企業の人手不足対策として、次のような取り組みを行っている企業が多いようです。
1、賃上げの実施、募集賃金の引き上げ
2、福利厚生の充実
3、人材育成・研修制度の充実
4、オフィス・工場など、職場の環境整備
5、ワークライフバランスの推進
6、多様で、柔軟な時間設定による働き方の推進(フレックス制、時短勤務など)
7、副業・兼業の許可
8、場所にとらわれない、柔軟な働き方の推進
1→8の順に取り組む企業が多いという並びになっています。
これらに魅力がないわけではありませんが、これらの要件で勝負するには、他社を圧倒する条件を用意しなければなりません。
しかし、それが可能な企業は稀です。
やらなければ企業価値を下げるが、やってもドングリの背比べという結果に終わるでしょう。
企業は防衛措置として、ある程度は上記の対策を行う必要がありますが、もっと本質部分に着手する必要があります。
それは「動機づけ要因」の充実です。
聞き慣れない言葉だと思いますが「働き甲斐」と解釈していただければOKです。
働く魅力には「待遇」と「働き甲斐」の2種類があります。
□待遇
具体例:賃金や福利厚生、職場環境など。
特徴:一定水準を下回ると不満足になるが、水準を満たしていたら、それ以上改善しても満足度は高まらない。改善すると瞬間的に嬉しいがすぐに慣れる。
□働き甲斐
具体例:承認、仕事を任せられていること。仕事そのものが愉しい。達成感など。
特徴:心から仕事が好きになる。仕事の行為自体から喜びを得ることができ、仕事に夢中になる。より向上させたいという「マスタリー感情」が生まれる。
これらは別物で、待遇を改善しても働き甲斐は高まりません。
日本商工会議所の調査で明らかになった企業の対策は、そのほとんどが待遇面です。
そんな企業が多い中で、働き甲斐を訴求できればキラリと光る存在になり、それを望む人と縁を結ぶ可能性が高まるということです。
こう言うと「働き甲斐を求める人がどれだけいるのか?」と否定的に捉える方がいますが、知らないだけで現代社会には大勢います。
いつの時代も、物質的に満たされると、それと逆行するように精神的な枯渇が生まれます。
例えば、19世紀終わりから20世紀の初頭にかけて、第二次産業革命の恩恵を受け、物質的な富を手にした時期に、街には「何のために生きているか分からない」という人が急増しました。
その処方箋として「幸福論」に関する書籍が立て続けに出版されました。
1960年代には、物質的な富を追求する資本主義へのアンチテーゼとしてヒッピームーブメントが興りましたね。
物質的な充足が一段落すると「生きる意味」などを考えるようになるのです。
そして、人はいつの時代も「希少なもの」を追い求めます。
働く意味、生きる意味が希少化している今、それを宣言する企業に人材が集まるのは当然のことです。
今日の話は単なる人手不足対策に留まりません。
働き甲斐を持った人は、高い自発性、創造性を発揮し、素晴らしい仕事をしてくれます。結果的に、企業力が増し、業績が良くなり待遇面も向上するのです。
是非とも、自社独自の働く意味を宣言し、素晴らしい人材と出会ってください。
今日の話は、指示ゼロ経営式 採用術の真髄です。
より詳しく知りたい方は10/22(水)に開催されるセミナーに起こしください。
きっと、これまでの採用の常識が覆されると思います。
↓詳細はこちら。