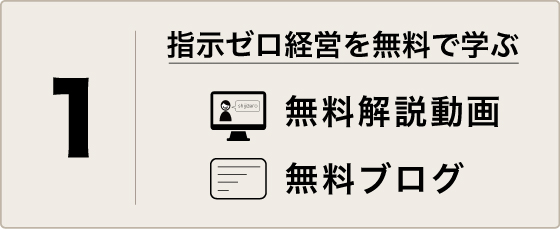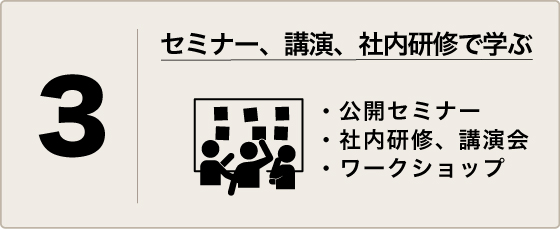組織腐敗の真犯人は誰だ? …経営者が直視すべき意外な黒幕
菓子製造大手のシャトレーゼが「不祥事の百貨店」の様相を呈しています。
2025年3月には、中小企業庁が実施した「下請け企業への代金支払い調査」で最低評価を受けました。5月には違法な時間外労働と、特定技能の在留資格を持つ外国人への休業手当の未払いが発覚しました。2024年10月には菓子に虫が混入していたが対応を放置。2023年には賞味期限の書き換えがありました。
産経新聞の取材に対し、社長は「急成長による歪が原因」とし「成長戦略をやめる」と答えています。
調べると、ここ10年で売上高は3倍ほどに成長しているんですね。
数々の行為はとても褒められたものではありませんが、僕は、社長の決断は潔いと思っています。
こうした不祥事に対し「社員教育を徹底します」と的はずれなコメント出す企業が多いのですが、原因は社員にはありません。100%経営者にあります。さらに言えば「仕組み」が原因です。
報道では明らかになっていませんが、同社の不祥事の背景には、急成長戦略だけでなく、数値重視の評価制度があったと推測します。
間違った戦略と評価制度が組み合わさると組織は腐敗するんですよね。
人の行動は仕組みで規定されます。
イジメが悪いと分かっていても、ある組織に属するとやってしまうのです。その組織には、強い競争原理(仕組み)が働いている可能性があります。
ドイチェという学者が提唱する「競争と共同」 によると、競争は、一部の人だけが達成できる目標を設定すると起こり、共創は、力を合わせないと達成できない目標の設定で必然的に起きると言います。 仕組み次第というわけです。
社内に好ましくない行為があるとしたら、まずはリーダーは仕組みを疑うことです。
風土ではなく仕組みです。
風土はメンバーの一挙手一投足で醸成され、一挙手一投足は仕事の仕組みで決まります。
だから、仕組みに着手しなければ改善はされないのです。
とても分かりやすい事例として、僕が所属した新聞業界を紹介します。
新聞ビジネスは「固定費ビジネス」と言われています。
日本で最も発行部数が多い全国紙は読売新聞で、およそ580万部。最も部数が少ない新聞は毎日新聞で、およそ150万部です。
これだけの差があっても、両者とも新聞製作にかかる費用に差はありません。最大の費用は記者などの人件費(固定費)です。
一方で、新聞自体の原価は紙とインクですので大したことはありません。
となると、多く売れば売るほど儲けの効率が良くなります。多く売った者が競争力を得て、より多く売れるのです。
この構造のもと、どんな営業が繰り広げられたかはご存知ですよね。
契約するまで帰らない営業マンがいたり、10年契約でスクーターをプレゼントしたりと、狂った営業がまかり通りました。
これを受け、業界では「販売正常化」を掲げ、何十年も取り組んできましたが、結局自浄は出来ませんでした。
風土は仕組みの帰結であり改善の入口ではありません。
よろしくない行為を改善しようと思ったら、生産の仕方に着手する必要があります。
ところで「業界っぽさ」ってありますよね。
「不動産屋さんっぽい」「建築業っぽい」「広告代理店っぽい」とか。
「ぽさ」とはまさに風土ですが、よくも悪くも、それは商売の生産方式に起因すると考えています。
自社の仕事のやり方と仕組みは、どんな「ぽさ」を生み出すか、一度考えてみてはいかがでしょうか。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。